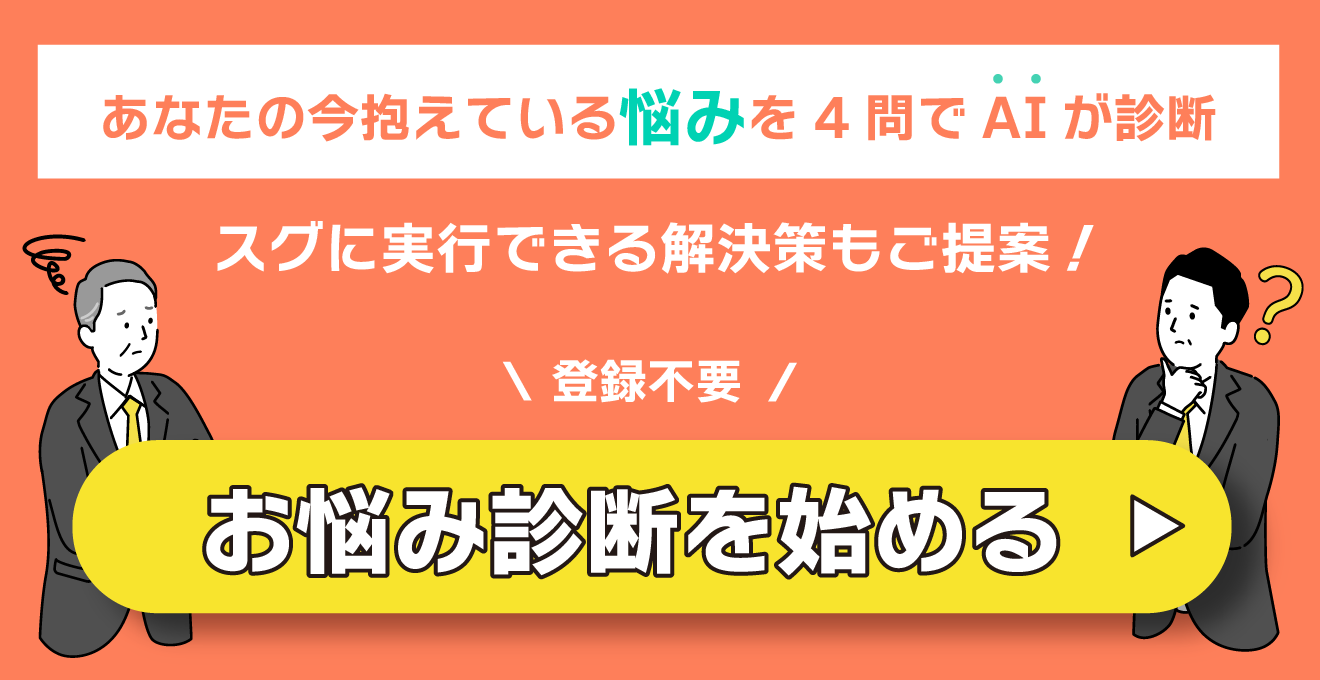この記事の目次
退職届の書き方は横書きでもOK?

退職届の書き方は「縦書き」が一般的とされていますが、「横書き」で書いても問題はありません。とくに近年は、Web上で退職届のテンプレートをダウンロードできるため、横書きとなっている場合も多く見られます。
ただし、会社の就業規則に退職届の形式が定められている場合があるので、作成前に必ず目を通しておきましょう。
また、横書きの場合、縦書きとは退職届の書き方が異なりますので注意が必要です。続いて解説する書き方のポイントや、退職届の例文を参考にしてみてください。
確認しておきたい退職届と退職願の違い

退職届と退職願では、提出するタイミングや目的、提出先などが異なっています。具体的に、どのような部分に相違があるのか比較してみましょう。
【退職届】
・提出するタイミング:退職が正式に確定したあとに提出します。
・提出する目的:退職が確定したことを証明する書類です。
・提出先:人事や労務担当者へ提出しましょう。
【退職願】
・提出するタイミング:初めて上司に退職の意を伝えるときに提出します。
・提出する目的:退職したい旨を願い出る書類です。
・提出先:直属の上司へ提出しましょう。
退職届を書くときに準備するもの3つ

退職届を書くときに準備するものは、「ペン」「便箋」「封筒」です。
いずれも100円ショップなどで安く購入できますが、紙質等あまりにも安く見えるものは避けた方がいいでしょう。また、ビジネス向きの白や無地など、シンプルなデザインを使用するようにしましょう。
1:ペンについて
黒色のボールペンか万年筆を用意しましょう。
油性・水性どちらでも問題ありませんが、インクがにじんで書面が汚れないよう注意が必要です。鉛筆やシャープペンシル、フリクションなどの消せるボールペンは、記載した内容が消えてしまうため利用は避けてください。
2:便箋について
サイズはA4かB5サイズ、白色で無地の便箋を用意しましょう。
縦書きの場合、罫線ありのものを使用するとまっすぐ綺麗に書けます。線がなくても綺麗に書ける自信がある場合は、コピー用紙でも代用が可能です。
なお、就業規則により退職届のフォーマットがあらかじめ決まっている会社もありますので、人事担当者に確認をとりましょう。
3:封筒について
白色で無地の和封筒を用意しましょう。
封筒の表面(通常切手を添付する面)に、「退職届」や「退職願」と記載するため、郵便番号枠などが印字されているものは避けてください。
便箋や用紙は三つ折りで封入します。A4であれば「長形3号」、B5であれば「長形4号」と、用紙にあわせた封筒を使用してください。
横書きでの退職届の書き方

横書きでの退職届の書き方と、縦書きでの書き方は記載内容の順序が異なります。ここでは、横書きで書いた場合の退職届例文を紹介しましょう。
1行目:中央に「退職届」と記載
2行目:右寄せで「届出年月日」を記載
3行目:左寄せで「退職する会社の正式名称」「代表社名」を記載
4行目:右寄せで「ご自身の所属部署」を記載
5行目:右寄せで「ご自身の氏名+印鑑(認印)」を記載
本文:私義(あるいは私事)
このたび、一身上の都合により、XXXX年XX月XX日をもって退職いたします。
文末:「以上。」と締める
上記例文の退職理由は、自己都合用となっています。その他、退職理由によって以下の例文を参考に「本文」の箇所を書き換えましょう。
▼自己都合で退職の場合
例文:このたび、一身上の都合により、XXXX年XX月XX日をもって退職いたします。
▼会社都合で退職の場合
例文1:このたび、退職勧奨に伴い、XXXX年XX月XX日をもって退職いたします。
例文2:このたび、部門縮小のため、XXXX年XX月XX日をもって退職いたします。
例文3:このたび、早期退職のため、XXXX年XX月XX日をもって退職いたします。
パソコンで横書きの退職届を作成するコツ

一般的には手書きでの作成が推奨されますが、パソコンで作成しても問題ありません。
インターネットで「退職届 テンプレート」と検索すると、無料で退職届のテンプレートをダウンロードできます。縦書き、横書きいずれも取得できるので、必要項目を入力し、簡単に作成が可能です。
退職届をプリントアウトして作成する際は、日付や名前など、テンプレートのまま提出することがないように確認しましょう。
ただし、会社指定のフォーマットが用意されている場合や、手書きでの作成を求める会社もあるので、不明な場合は人事担当者に問い合わせてみるといいでしょう。
退職届を封筒に入れるポイント

退職届は担当者へ手渡しする場合でも、封筒に入れて提出するのが一般的です。
和封筒の表面中央に縦書きで「退職届」あるいは「退職願」と記載します。また、裏面左下には、自身の所属部署と氏名を2行に分けて記載してください。
その他、便箋の折り方や封筒への入れ方にも決まりがありますので、以下に紹介します。
折り方について
便箋は「三つ折り」で折りましょう。
まず、書類の文面が見えるように机に置きます。次に長辺を3分割したあと、下から上に3分の1を折り上げます。それから、上部3分の1を下へ折り重ねて完成です。
角と角がずれないように、定規を使うと綺麗に折ることができます。
入れ方について
封筒への入れ方にも決まりがあります。
退職届や退職願の文面が見える状態で右上部分が、封筒の裏面(通常自分の住所や名前を記載する面)の右上と重なるように入れます。
封筒を受け取った相手が、書類を開けたときに「退職届」あるいは「退職願」の文字を最初に目にするようにしましょう。また、書類がシワにならないよう、丁寧に入れましょう。
なお、手渡しの場合は封はしなくても良いでしょう。郵送の場合は、封をして「〆」マークを記載しましょう。
退職届や退職願を出す時期

退職届や退職願は提出する時期が異なります。
「意向を示す」際に提出するものなのか、「退職が決定した」際に提出するものなのか、状況を確認した上で準備しましょう。
また、就業規則により退職日から起算して何日前までに書類を提出するよう定められている場合もあります。必ず確認をしましょう。
退職の意向を示すときに退職願を提出する
退職願は、退職の意向を初めて上司に示すときに提出する書類です。
この時点で、退職は確定していません。あくまでも退職したい旨を願い出る内容であり、会社側は退職願をもって退職承諾の検討に入ります。そのため、会社が承諾するまでは撤回できるとされています。
退職が決定したときに退職届を提出する
退職届は、退職が確定した際に会社へ提出する書類です。原則、受理されたあとに撤回することはできません。
会社ごとに提出する書類や提出先が異なる場合があるので、分からない場合は人事担当者へ問い合わせてみましょう。
退職届や退職願についての疑問3つ

ここからは、退職届や退職願を提出する際のよくある疑問を3つご紹介します。
例えば、会社都合で退職する場合もあれば、退職届や退職願が必要ないと言われる場合もあるでしょう。また、退職届を書いたにもかかわらず、上司に受け取ってもらえないという場合もあるでしょう。
そのようなときの対処法を、以下で詳しく見て行きます。
1:会社の都合の場合はどうする?
会社都合の退職で、手続き上退職届の提出を求められた場合は、就業規則を確認するか、人事担当者に直接問い合わせましょう。
また、退職届に記載する理由については「会社都合で退職となる旨」を明確に記載する必要があります。
その他にも「退職勧奨に伴い」「部門縮小のため」「早期退職のため」などの書き方があります。書き方は状況に応じて変更し、間違っても自己都合と捉えられないようにしましょう。
2:退職届や退職願を提出しなくもいいと言われたら?
退職届は、後々のトラブルを防ぐためにも証拠として書面で提出することが望ましいです。
担当者に受け取りを断られた場合でも「形として残しておきたいため、提出いたします」と伝えましょう。
なお、退職願は退職確定前に提出する「打診のための書類」ですので、必ずしも提出する必要はありませんが、不安な場合は確認しておきましょう。
3:退職届の受け取りを拒否された場合は?
直属の上司に退職届の受け取りを拒否された場合は、さらに上の役職者や人事担当者に相談しましょう。
法律上、口頭であっても退職の意思表示をした場合、その後2週間が経過すれば退職は成立します。しかし、書面として残さない場合、後々トラブルになる可能性があります。
どうしても受け取ってもらえない場合は、「内容証明郵便」で退職届を会社に郵送しましょう。
内容証明は、「いつ、どのような文書を誰から誰宛てに送付されたか」について、差出人が作成した謄本によって日本郵便局が証明する制度ですので、こちらから確実に送付した証明になります。
退職届の横書きの書き方について知ろう
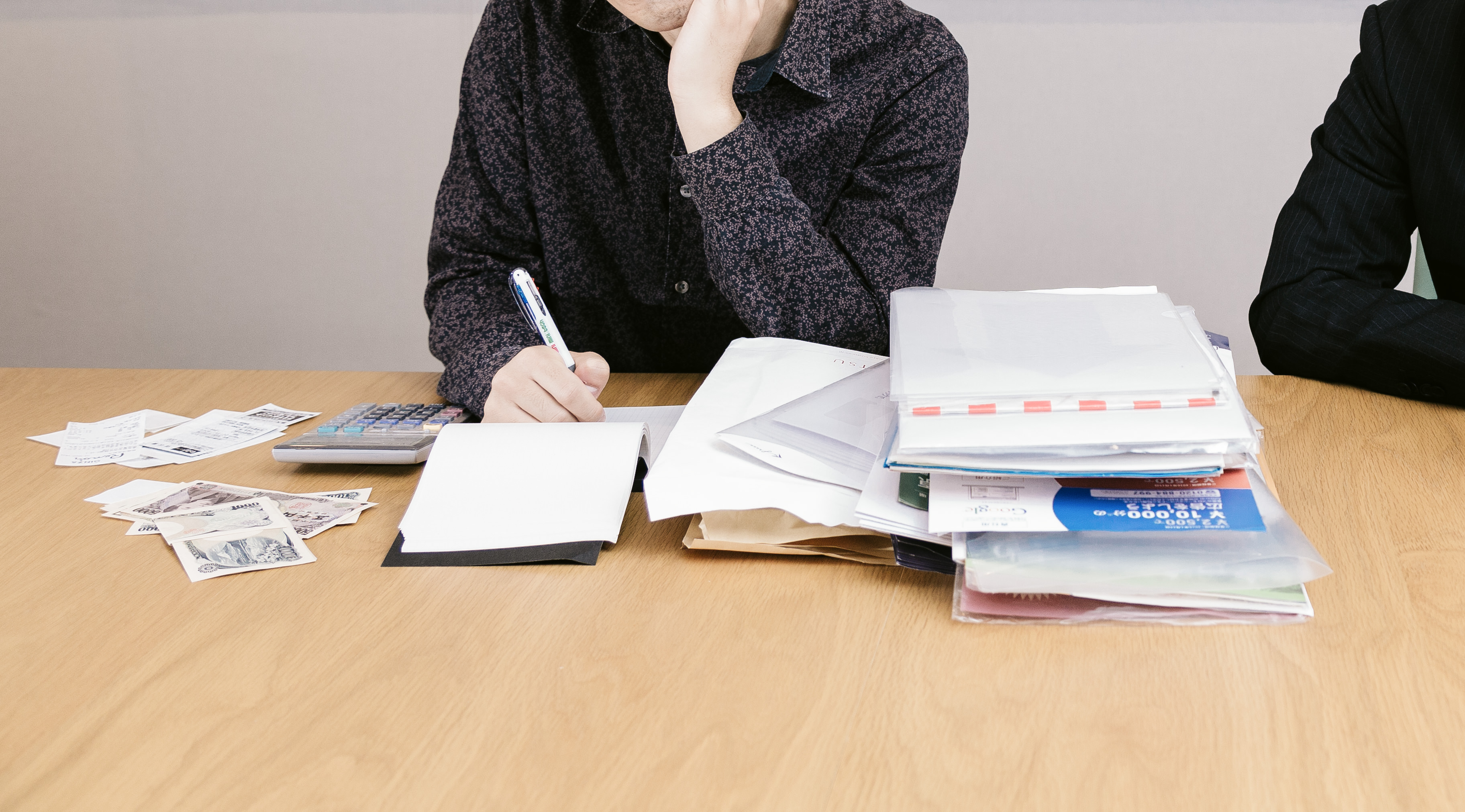
退職届を書く際は、横書きでも問題ありません。
手書きで何度も失敗してストレスを感じてしまうよりも、既存のテンプレートや会社が用意しているフォーマットを利用して、退職届を効率的に作成しましょう。
会社独自の規則やルールもありますので、不明な点は上司や人事担当者などに書き方を確認した上で準備しましょう。
この記事の監修者・著者

-
未経験からITエンジニアへのキャリアチェンジを支援するサイト「キャリアチェンジアカデミー」を運営。これまで4500人以上のITエンジニアを未経験から育成・排出してきました。
・AWS、salesforce、LPICの合計認定資格取得件数:2100以上(2023年6月時点)
・AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
最新の投稿
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】