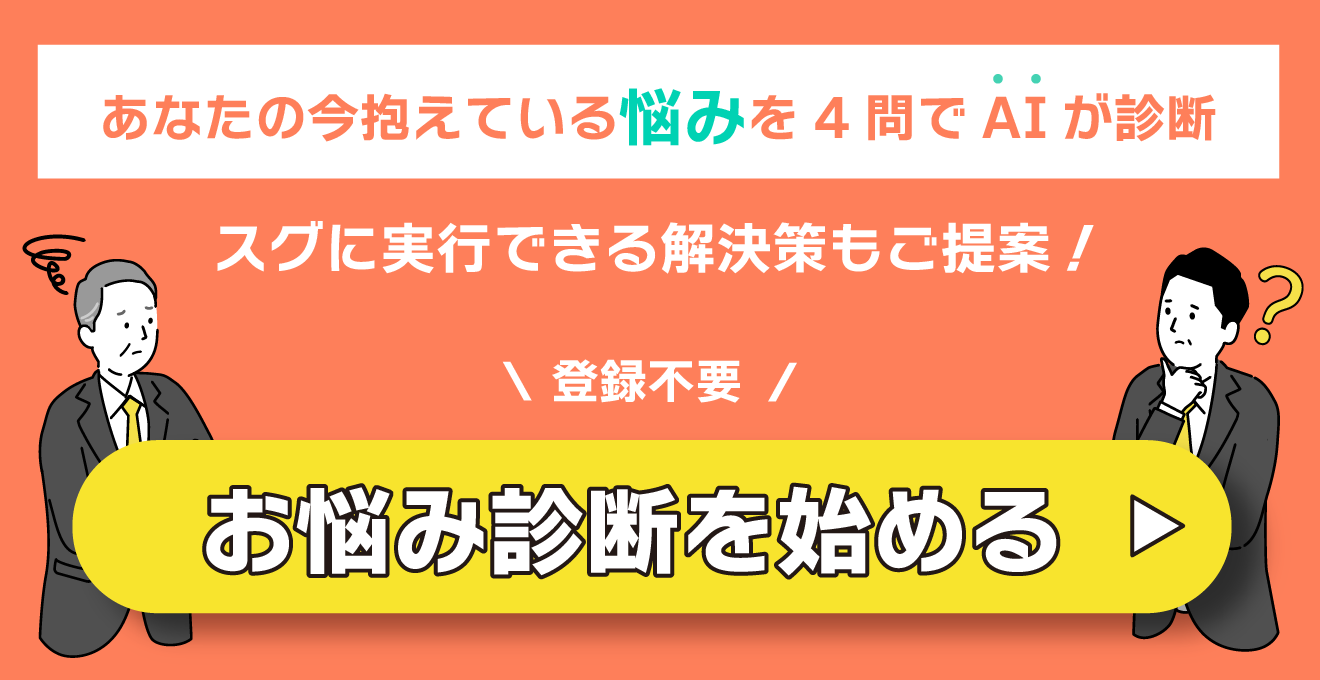インフラエンジニアがAWSでサーバー構築する「運用編」についてお送りします。
AWSで立てたサーバーの運用方法
AWS(Amazon Web Services)はAmazonが提供するクラウドサービスです。AWSを利用すれば簡単にサーバーを立てることも可能になります。 レンタルサーバー事業者はバックアップや監視、セキュリティ対策も含めたサービスとなっていることが多いですが、AWSには基本的にそれがありません。 しかし、AWSは基本的に無料か格安で利用できる代わりに、バックアップや監視、セキュリティ対策などはユーザー自身で行う必要があります。 これらの運用は、一般的にはインフラエンジニアが担当することも多いです。
AWSで運用するメリット
AWSのメリットは何といっても初期費用が無料な点です。 従来の物理的に設置していたサーバー構築をすべてクラウド上で行うことで、初期費用を抑えられます。大型の初期投資が不要になり、柔軟にITリソースを確保できます。
AWSで立てたサーバーの特徴
例えばAWSのサービスのひとつである「Amazon EC2」は、仮想マシンをウェブサービスとして提供できます。 APIのコールひとつで、複数のEC2インスタンスタイプ、アベイラビリティゾーンなどをプロビジョニングできます。 また、柔軟なストレージオプションがあるのも特徴です。 組み込みのインスタンスストレージだけでなく、Amazon Elastic Block Store (EBS) や、 Amazon Elastic File System (EFS)などのクラウドストレージにも対応しています。
従量課金制を採用
AWS必要な時に必要な分だけ支払う「従量課金制」を採用しているのも特徴です。 例えば、繁忙期など多くのITリソースが必要となった時には必要な分だけ増強し、閑散期には少なくするという手段も使えます。 不要になった際にはサーバーを停止し、データを削除することで課金されなくなります。 新しいプロジェクトを立ち上げたい時や、素早くサービス検証などを行いたい時にも便利です。
インフラエンジニアが今後も利用することの多いサービス
AWSを採用している企業は増えており、今後もその増加の一途をたどると考えられています。 そのためインフラエンジニアはクラウドサービスのスキルを身に付けるとともに、AWSで構築・運用の想定をしておくことをおすすめします。
この記事の監修者・著者

-
未経験からITエンジニアへのキャリアチェンジを支援するサイト「キャリアチェンジアカデミー」を運営。これまで4500人以上のITエンジニアを未経験から育成・排出してきました。
・AWS、salesforce、LPICの合計認定資格取得件数:2100以上(2023年6月時点)
・AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
最新の投稿
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】