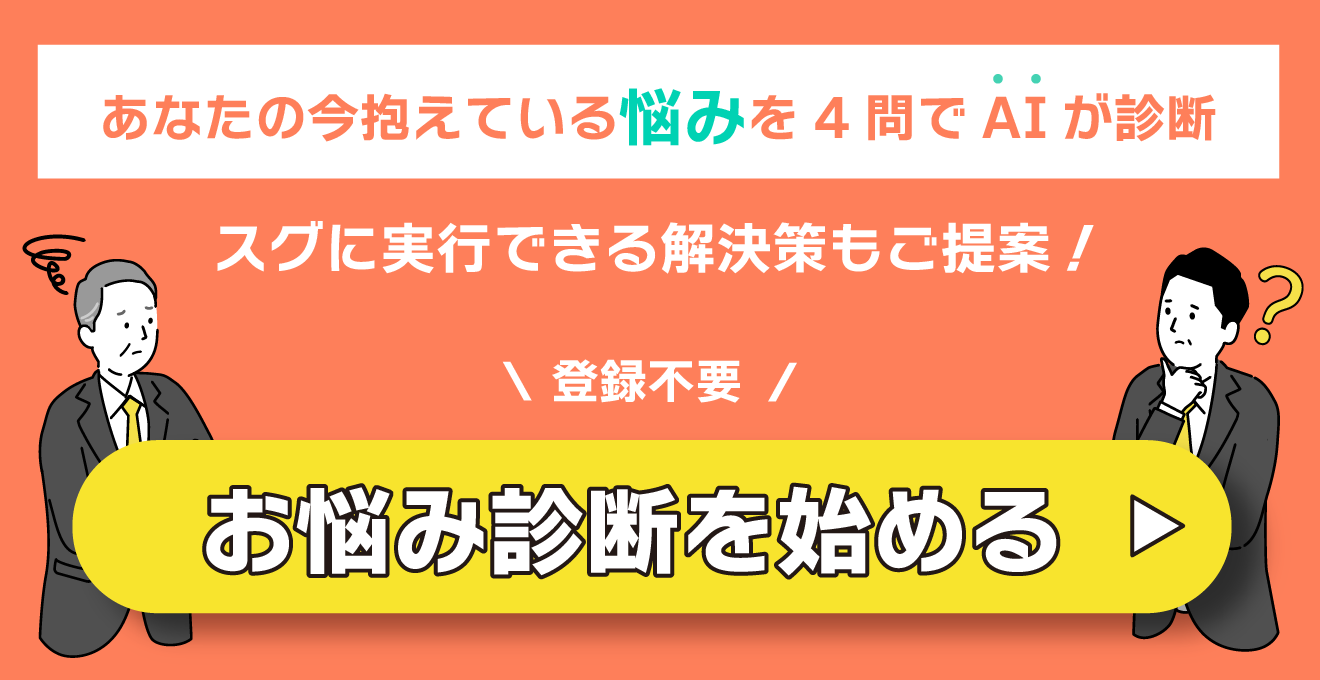この記事の目次
- そもそもAWS認定試験とは?
- AWS認定試験の資格6つ
- AWSのSAPにおける勉強方法12選
- AWSのSAPにおける勉強方法1:BlackBeltを活用する
- AWSのSAPにおける勉強方法2:LinuxAcademyやUdemyなどを利用する
- AWSのSAPにおける勉強方法3:koiwa clubを利用する
- AWSのSAPにおける勉強方法4:実際に構築してみる
- AWSのSAPにおける勉強方法5:模擬試験を受ける
- AWSのSAPにおける勉強方法6:模擬結果を踏まえて勉強する
- AWSのSAPにおける勉強方法7:ノートにまとめて勉強する
- AWSのSAPにおける勉強方法8:問題の内容をイメージする力を養う
- AWSのSAPにおける勉強方法9:ITの基礎知識を身につける
- AWSのSAPにおける勉強方法10:問題集を繰り返し解く
- AWSのSAPにおける勉強方法11:AWSの各サービスを把握しておく
- AWSのSAPにおける勉強方法12:コストを意識する
- SAP以外のAWS認定試験に関する勉強方法5つ
- 学習ポイントを押さえてAWSのSAP資格の合格を目指そう!
そもそもAWS認定試験とは?

AWS認定試験とは専門的なクラウド知識を持ち、AWSを利用する高いスキルを持つことを認定する試験です。
Amazonが提供しているAWS(Amazon Web Services)というクラウドコンピューティングサービスを利用するためのさまざまなスキルを認定する試験です。
AWS認定試験は分野や専門ごとに12種類にわかれており、近年AWSの需要拡大に伴いAWS認定試験の需要も高まってきています。
AWS認定試験の資格6つ

AWS認定試験にはさまざまな資格があります。
AWS認定試験は技術的な分野からは独立した「基礎コース」と、アーキテクト、運用、デベロッパーという3つの分野にわかれた「アソシエイト」と「プロフェッショナル」、さらに「専門知識」に分かれています。
ここではAWS認定試験の資格6つをご紹介しますので、どのような資格があるのか参考にしてみてはいかがでしょうか。
AWS認定試験の資格1:SAP
SAPはソリューションアーキテクトの上位資格です。
SAPは「AWS認定ソリューションアーキテクト−プロフェッショナル」の略で、2年以上のAWSを利用したシステムの管理や運用の実務経験を持つ設計者を対象としています。
試験では主に動的なスケーラビリティや高可用性、高い信頼性を持つアプリケーション設計やデプロイなどの知識とスキルが問われます。
AWS認定試験の資格2:SysOps
SysOpsは運用担当者向けの資格です。
SysOpsは正式名称を「AWS認定SysOps アドミニストレーター」という資格で、高い可用性を持つシステムの開発や管理、運用のためのAWS技術やサービスについての知識やスキルが問われます。
また、SysOpsのレベルはアソシエイトレベルのみとなっており、SysOpsの上位試験はDeveloperと共通のDevOpsエンジニアプロフェッショナルとなっています。
AWS認定試験の資格3:SAA
SAAは設計者を対象とした資格です。
SAAは「AWS認定資格ソリューションアーキテクト – アソシエイト」の略で、AWSを使用した分散システムの可用性やコスト効率、高耐障害性、スケーラビリティの設計などの1年以上の実務経験がある担当者を対象としています。
また、主にシステムの設計や構築、運用を行う上でのベストプラクティスに沿った問題が出題されます。
AWS認定試験の資格4:DevOpsエンジニア
DevOpsエンジニアは運用担当や開発者向けの上位資格です。
DeveloperとSysOpsアドミニストレーターの上位資格で、2年以上のAWS環境の運用や管理の実務経験を持つエンジニアを対象とした試験です。
DevOpsエンジニアを取得することで、AWSを使用した高い可用性や自己修復機能を搭載したシステム構築における専門的なスキルを証明することができます。
AWS認定試験の資格5:Developer
Developerは開発者向けの資格です。
クラウドプラクティショナーの上位にあたる試験で、試験では主にシステム構築において拡張性やコストを考慮するための手法やサービスの選択について問われます。
また、Developerを取得することで、AWSを利用したアプリケーション開発のスキルを証明することができます。
AWS認定試験の資格6:クラウドプラクティショナー
クラウドプラクティショナーは基礎レベルの資格です。
AWS認定における入門レベルの試験で、試験ではクラウドの概念やセキュリティやテクノロジーなど請求と料金について問われます。
また、AWSに関する基礎的な知識を持っていることを証明できる資格となっており、6か月程度のAWSクラウドとIT業界に関する知識を持った人材が対象となりますが、実務経験がなくても独学で取得しやすい資格です。
AWSのSAPにおける勉強方法12選

AWSのSAPのおすすめの勉強方法をご紹介します。
これからAWSのSAPに挑戦しようと考えている方の中には、SAPの勉強方法に関する情報があまり見つからず困っているという方もいるのではないでしょうか。
ここではAWSのSAPにおける勉強方法12選をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
AWSのSAPにおける勉強方法1:BlackBeltを活用する
AWSのSAPの勉強には、BlackBeltを利用しましょう。
BlackBeltとは「AWSクラウドサービス活用資料集」のことで、AWSの各種サービスの利用に役立つ日本語の資料をまとめたものです。
プロダクト別の解説やアップデート情報など、AWSのサービスについてわかりやすくまとめられているため、AWSのサービスについて学ぶ場合は、まずはBlackBeltを見ると良いでしょう。
AWSのSAPにおける勉強方法2:LinuxAcademyやUdemyなどを利用する
AWSのSAPの勉強には、LinuxAcademyやUdemyなどを利用しましょう。
どちらもオンラインで利用できる学習サービスで、AWSに関する講座があります。Udemyは入門者向けから上級者向けまで幅広く揃っており、Linux Academyは全編英語ですが細かい内容まで解説してくれます。
そのため、英語スキルがある場合は、Linux Academyを利用するのも良いでしょう。
AWSのSAPにおける勉強方法3:koiwa clubを利用する
AWSのSAPの勉強には、koiwa clubを利用しましょう。
koiwa clubとは「AWS WEB問題集で学習しよう」という名前のオンラインのAWSの学習サイトです。7問単位の問題集になっているため、すきま時間でも学習を進められます。
また、WEB問題集では解説部分にAWSのリンクが張ってあるため、解説とリンク先を確認しながら理解を深めていくようにしましょう。
AWSのSAPにおける勉強方法4:実際に構築してみる
AWSのSAPの勉強には、実際にAWSで構築してみましょう。
AWSには「AWS Hands-on for Beginner」という解説動画を見ながら、実際にAWSを利用して学べるサービスがあります。このサービスを利用して、実際に構築してみるのがおすすめです。
また、このサービスは2時間程度ありますが、いつでも視聴できるため、時間がある程度まとまって空いたときに利用すると良いでしょう。
AWSのSAPにおける勉強方法5:模擬試験を受ける
AWSのSAPの勉強には、模擬試験を利用しましょう。
AWSの模擬試験は受験料がかかりますが、本番試験の雰囲気を掴むのに最適です。すべての問題を解き終わると、合否や分野別正解率などが表示されます。
模擬試験に挑戦することで、自分の苦手な分野や意味のわかりにくい用語などがわかるようになるため、模擬試験の問題はキャプチャを取っておき、後から改めて復習できるようにしましょう。
AWSのSAPにおける勉強方法6:模擬結果を踏まえて勉強する
AWSのSAPの勉強には、模擬試験の結果を踏まえて勉強しましょう。
模擬試験によって自分がよくわかっていなかった用語や概念などが判明するため、1問ずつ見返しながらBlack BeltやAWSドキュメントなどを使って改めて調べていきましょう。
全問分すべて調べ、問題文と選択肢について、なぜそうなるのかが理解できるようになる必要があります。
AWSのSAPにおける勉強方法7:ノートにまとめて勉強する
AWSのSAPの勉強では、ノートにまとめて勉強しましょう。
模擬試験やサンプル問題などを利用した際に、自分が間違えた問題やわからなかった用語、忘れそうな内容は、すべてノートにまとめるようにしましょう。
自分が苦手な内容をノートにまとめて、まめに見直すことにより、正しい答えや意味を頭の中に定着させていくことができます。
AWSのSAPにおける勉強方法8:問題の内容をイメージする力を養う
AWSのSAPの勉強では、問題内容をイメージする力を養いましょう。
SAPの問題は長文になっており、内容を正しく理解するためには何度も読み直す必要があります。また、試験時間も180分と長く、問題数も75問あるため、できるだけ問題をスムーズに解けることが重要です。
そのため、問題の内容をイメージする能力を身につけることで、文章の意味を早く理解できるようになりましょう。
AWSのSAPにおける勉強方法9:ITの基礎知識を身につける
AWSのSAPの勉強には、ITの基礎知識を身につけましょう。
SAPの資格を取るには、AWSの知識だけでなく、基本的なITの知識があることが前提となります。たとえばネットワークやサーバー、データベースやSQL、システム構築などの基本知識は身につけておきましょう。
ITの知識があることで、具体的なAWSのサービスの活用方法などもわかるようになります。
AWSのSAPにおける勉強方法10:問題集を繰り返し解く
AWSのSAPの勉強には、問題集を繰り返し解いてみましょう。
問題集は一度解いて終わりではなく、2週目3週目と繰り返し説くことで、本番の試験でも問題を解く実力が身についていきます。1週目では解けなかった問題も、繰り返し解くことで正解率を上げていくことができます。
また、時間的な余裕があれば、1冊だけでなく別の問題集も解くと良いでしょう。
AWSのSAPにおける勉強方法11:AWSの各サービスを把握しておく
AWSのSAPの勉強には、AWSのサービスについて理解を深めておきましょう。
AWS認定試験では、当然AWSの各種サービスについて問われます。そのため、各サービスがどのようなものなのか把握しておきましょう。
たとえば、AWS特有のサービスや既存システムをクラウドに置き換えることができるAWSのサービス、セキュリティに関するサービスについては、しっかりと押さえておきましょう。
AWSのSAPにおける勉強方法12:コストを意識する
AWSのSAPの勉強には、コストについて意識しましょう。
SAPの問題では、問題文の要件を満たす選択肢が2つ以上あり、コスト効率などの優先順位が高い選択肢を選ぶケースがあります。そのため、残った選択肢の中から正しい答えを選べるように、AWSのサービスのコストについても意識を向ける必要があります。
SAP以外のAWS認定試験に関する勉強方法5つ

SAP以外のAWS認定試験に関する勉強方法をご紹介します。
ここまでSAPの資格試験に関するさまざまな勉強方法を紹介してきましたが、SAPはプロフェッショナルレベルとなるため、他の試験を受けるという方も多いでしょう。
ここでは最後にSAP以外のAWS認定試験に関する勉強方法5つをご紹介しますので、AWS認定の他の資格取得を目指す際の参考にしてみてはいかがでしょうか。
勉強方法1:SysOpsの場合
SysOpsを受験する場合、運用をメインとしたさまざまな知識を身につける必要があります。
SysOpsの出題分野はモニタリングや高可用性、デプロイ、セキュリティ、ネットワーキング、分析、データ管理などです。試験範囲はSAAと被りますが、運用の比率が多くなります。
そのため、SysOpsを受験する場合は、先にSAAを受験することで、AWSの全体的な知識を身につけてから受験する方が難易度は下がるでしょう。
勉強方法2:SAAの場合
SAAを受験する場合、AWSの各サービスに関する知識や設計について知識を身につける必要があります。
AWSの各サービスの特徴や、「AWS Well-Architected Framework」の5つの柱やベストプラクティスなどに関する問題が出題されます。
また、アソシエイトレベルの認定試験の中ではもっとも幅広い知識が必要となるため、公式ドキュメントやBlackBeltで網羅的に学習する必要があります。
勉強方法3:DevOpsエンジニアの場合
DevOpsエンジニアを受験する場合、要件に応じたソリューションを選択できる知識を身につける必要があります。
SAPと同様にプロフェッショナルレベルとなるため、難易度が高い試験です。また、試験範囲も広いため、SAPと同じように学習サイトや問題集、模擬試験などを活用して学習を行いましょう。
勉強方法4:Developerの場合
Developerを受験する場合、AWSの各サービスに関する知識やデプロイツール、デバッグについて知識を身につける必要があります。
AWS認定資格の中では開発者向けの資格で、AWSの各サービスやセキュリティ、リファクタリング、モニタリング、トラブルシューティングなどについて問われます。試験範囲はSAAよりも絞られます。
勉強方法5:クラウドプラクティショナーの場合
クラウドプラクティショナーを受験する場合、AWSの基礎知識を身につける必要があります。
AWS認定資格の中では入門レベルの試験となるため、AWS公式のドキュメントや書籍などを利用して学習を行いましょう。出題分野もクラウドの概念、セキュリティ、テクノロジー、請求と料金という4つのテーマのみです。
学習ポイントを押さえてAWSのSAP資格の合格を目指そう!

AWS認定試験にはさまざまなレベルや分野の資格があります。
ぜひこの記事でご紹介したAWS認定試験の資格やAWSのSAPの勉強方法などを参考に、AWS認定試験のソリューションアーキテクトのプロフェッショナルレベルであるSAPの資格取得を目指してみてはいかがでしょうか。
この記事の監修者・著者

-
未経験からITエンジニアへのキャリアチェンジを支援するサイト「キャリアチェンジアカデミー」を運営。これまで4500人以上のITエンジニアを未経験から育成・排出してきました。
・AWS、salesforce、LPICの合計認定資格取得件数:2100以上(2023年6月時点)
・AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
最新の投稿
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】