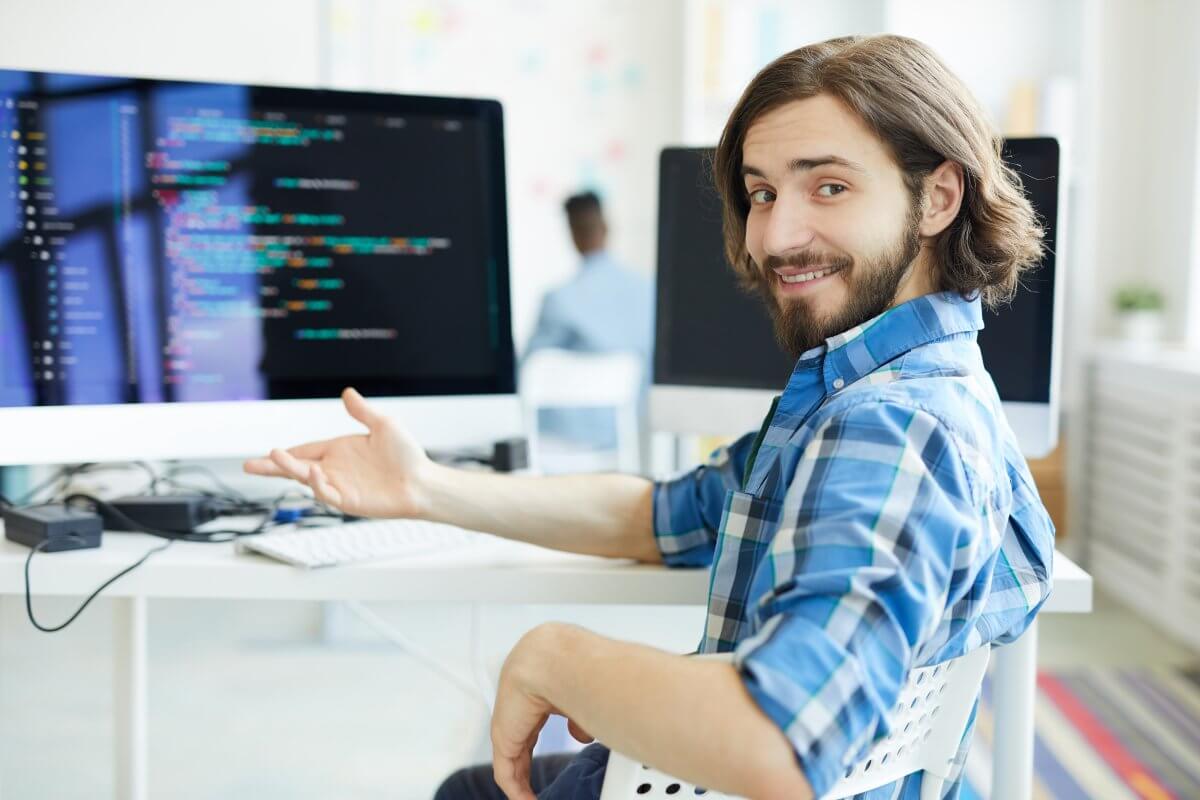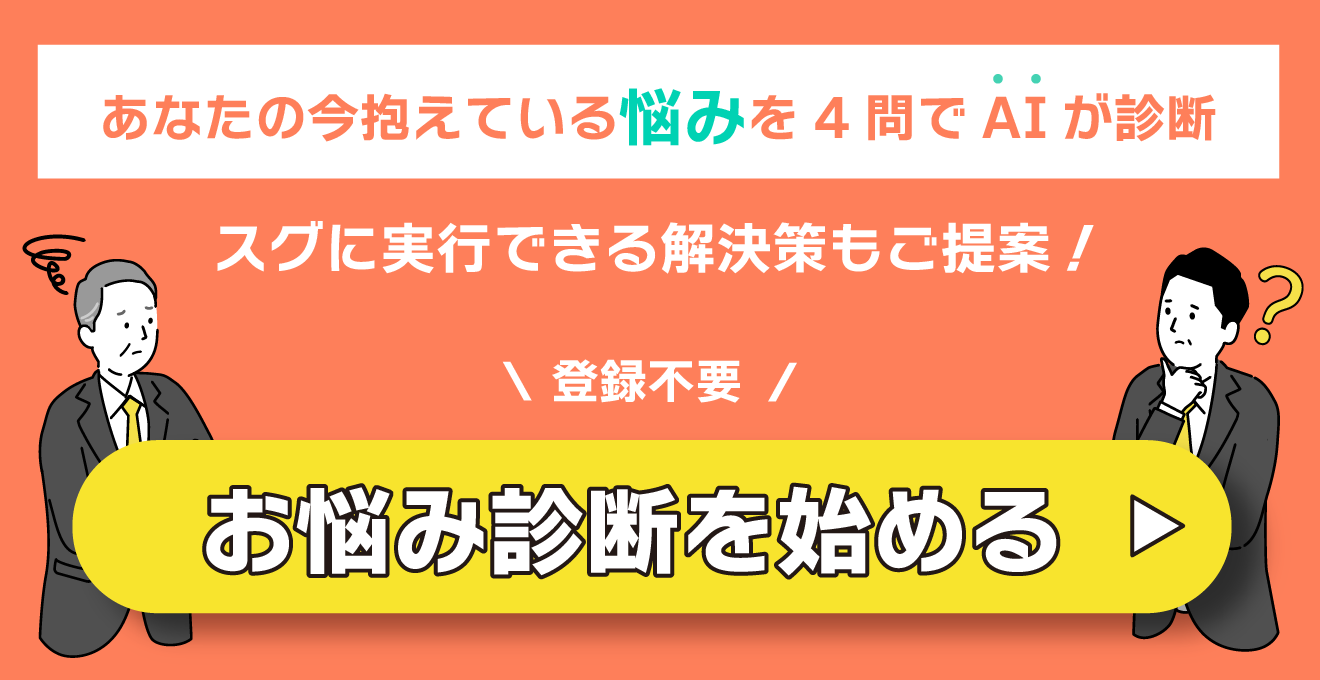この記事の目次
AWS(アマゾンウェブサービス)とは?

AWS(Amazon Web Service)とは、Amazonが提供しているクラウドサービスの総称です。
Amazon Web Serviceと称していますが、提供しているのはWeb Serviceに限りません。世界中のデータセンターを利用し、175以上もの機能がある多彩なインフラストラクチャーサービスを提供しています。
今では、スタートアップ企業、大手企業、政府機関など、何百万もの顧客が利用しているサービスです。
他に、Microsoft AzureやGoogle Cloud Platform、Oracle Cloudなど、数あるクラウドプラットフォームの中でも、特にAWSは利用する企業が増えていくと予測されています。
そのため、AWSを導入する企業のさらなる増加と共に、相応の技術を持ち合わせたAWSエンジニアの需要増加が見込まれています。
AWSの仕組みと技術

AWSとは、Amazonが所有するIT資源や機能をインターネット経由にて、利用場所を問わず、セキュアに利用できる従量課金制の仕組みです。AWSの仕組みを理解するためには、AWSによって実現できることを知る必要があります。
AWSは、オンプレミス(物理サーバを自社で運用すること)とは違い、クラウドコンピューティング(インターネット経由でIT資源を利用すること)を提供するサービスです。
クラウドコンピューティングサービスは、利用場所の制限を受けず、バックアップ取得やパッチ適応などの運用作業を自動化することが可能です。
また、多種多様なアプリケーション専用に設計されたデータベースを提供しているため、機械学習や人工知能などの新しいテクノロジーを構築することもできます。
さらに、仮想サーバ作成、セキュリティー対策、コンテンツ配信、大量のメール送信など、まだまだ、AWSで実現できることが数多くあります。
AWSエンジニアに必要な知識と技術

- AWSに関する技術的な知識
- AWSでのサーバ設計、構築、運用、保守に関する知識と技術
- AWSでのアプリケーション、システム設計、構築、運用、保守に関する知識と技術
AWSエンジニアに必要な知識と技術は、上記に挙げた3点で、ほとんどカバーされます。ですが、抽象的で、実際どうしたらよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。
AWSの仕組みや、実現できることを理解できてくると、AWSエンジニアに必要な知識や技術が、少しずつみえてきます。
主にオンプレミスでの企業システムを構築するインフラエンジニアに求められる技術は、システム開発、ハードウェア、サーバ、ネットワーク、セキュリティーなどの知識や技術が必要です。最近では、同時にクラウドでの知識や技術も必要な場面も多くなっています。
ですが、ネットワーク経由のクラウド型で、175以上の機能があるAWSのエンジニアに求められる技術は、多少異なります。
一般的なインフラエンジニアと異なるのは、AmazonのIT資源や機能に依存するサービスのため、AWSの専門的な知識や技術も必要になることです。
AWSエンジニアになるためには?
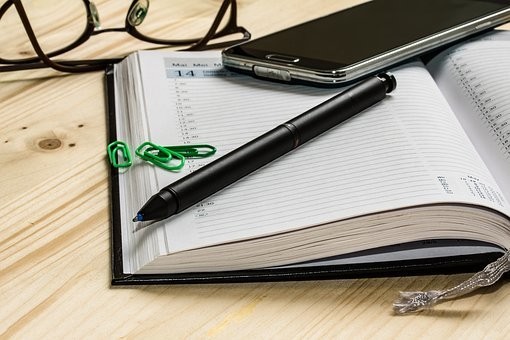
AWSエンジニアになるためには、AWSの専門知識や技術が必要です。
ここまでの内容を見てくると、AWSエンジニアになるためには、インフラエンジニアの基本知識や技術に加え、多大なAWSサービスを全て勉強する必要があるのではないかと、そのハードルを高く感じる人は少なくないでしょう。
ですが、その心配の必要はありません。なぜなら、これから紹介するAWSエンジニアとして、必要最低限の知識と技術を取得しておけば活躍できるからです。
では、一体その技術や知識を取得する方法とは何なのか、また、何から始めていけばよいのか、AWSエンジニアになるための方法を、一つずつ順番に紹介していきます。
AWSアカウントを作成しましょう
まずは、AWSのアカウントを作成します。法人・個人どちらとしても、WEB上で作成できます。
登録に必要な情報は、AWSログイン情報(Eメールアドレス、パスワード、アカウント名)、連絡先情報(フルネーム、住所、電話番号)、支払い情報(クレジットカードかデビットカード)の3つです。
お支払い情報まで進むと、最後にサポートプランを選びことになります。ベーシックプラン(無料)、開発者プラン(有料)、ビジネスプラン(有料)の3つから選べます。
登録が完了すると、AWS(Amazon)から登録したメールアドレス宛てに「AWSの開始方法」を紹介する内容のメールが届きます。その開始方法に従い進んでいくと、AWSを利用する手順が分かる公式ページへと導かれていきます。
AWS利用料金を確認しましょう
AWSは、従量課金制であるため、使った分の料金が発生するサービスですが、最初にサインアップした日から12ヵ月間は、無料で利用できます。
有料枠でのスタートも可能ですが、無料枠としてスタートする場合は、毎月750時間分のLinux仮想マシン利用など、サービス毎に利用枠が設定されています。それぞれのサービスで無料利用枠を超えてしまうと、無料期間であろうとも課金されますので注意しましょう。
無料枠、有料課金単位などは、サービス毎に異なります。利用料金は、AWSログイン後、アカウント > 請求とコスト管理と進む画面で確認できます。
AWSを学びながら使ってみましょう
AWS公式サイトには、AWSエンジニアとして必要な知識、技術の情報が無料の範囲でも充分に記載されています。
初めての方でも、チュートリアルのラーニングパスが用意されていますので、動画を視聴しながら、WEBアプリケーションの構築方法などを学ぶことができます。
AWS公式サイトに掲載されている情報は、AWSエンジニアになるためには必要な基礎知識から、レベルアップのデジタルトレーニング、技術習得を証明する認定資格、技術向上のためのオンラインセミナーなど、親切丁寧に説明されています。
そのことから、AmazonがAWSのシェア拡大を目指し、AWSエンジニア育成にとても力を入れていることがよくわかります。この大きな波をタイミング良く大いに利用していきましょう。
AWSの技術サポートを受けたいとき
AWSを学びながら使用していくうちに、トラブルシューティングから抜け出せなくなることや、操作設定方法が分からなくなることがあるでしょう。
そのような場合、AWSサポートへの電話番号は設けられていませんが、Web、チャット、電話(AWSサポートから電話する)での技術サポートが受けられます。
先に、AWSアカウント作成で説明していたサポートプランには、実は、ベーシック(無料)、デベロッパー(有料)、ビジネス(有料)、エンタープライズ(有料)の4つのプランがあります。
登録時には選べない項目がありますが、登録完了後、いつでも変更できるプランとなっています。
また、AWSナレッジセンターでは、よくある質問に対して解決方法を日本語の動画で紹介してくれていますので、活用していきましょう。
AWS認定を取得しましょう
AWS認定とは、AWSの技術的スキルとクラウドの専門知識を取得したことの証明として、Amazonが公式で発行する認定資格です。AWSエンジニアになるために、取得しておきたいものです。
AWS認定試験の難易度は、基礎レベルのクラウドプラクティショナー(難易度低)、AWS認定アソシエイトレベル(中難易度)、AWS認定プロフェッショナルレベル(高難易度)、AWS認定専門知識(高難易度)と、4つに分けられています。
AWS公式サイトでは、無料のオンライン講座やサンプル問題が用意されており、模擬試験を受けることも可能です。また、AWS認定試験は、現在オンラインで受験することもできます。
IT社会で活躍できるAWSエンジニアへと成長する

まずは、AWSアカウントを作成し、AWSエンジニアへの第一歩を進めていきましょう。
そして、AWS公式で公開されている無料のトレーニングやAWS認定を利用してみましょう。AWSを理解できてくると、その可能性がより幅広く見えてきます。
現在、IT業界では、オンプレミスから設備メンテナンス不要で安価なクラウドへの移行が進んでいます。それ故、これからもAWSは、さらにシェアを拡大していきます。
「急速に進化していく未来で、AWSの知識と技術を習得し、AWSエンジニアとして活躍できる人材へと成長していく」その様な自分の成長した姿を、想像できたのではないでしょうか。
この記事の監修者・著者

-
未経験からITエンジニアへのキャリアチェンジを支援するサイト「キャリアチェンジアカデミー」を運営。これまで4500人以上のITエンジニアを未経験から育成・排出してきました。
・AWS、salesforce、LPICの合計認定資格取得件数:2100以上(2023年6月時点)
・AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
最新の投稿
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】