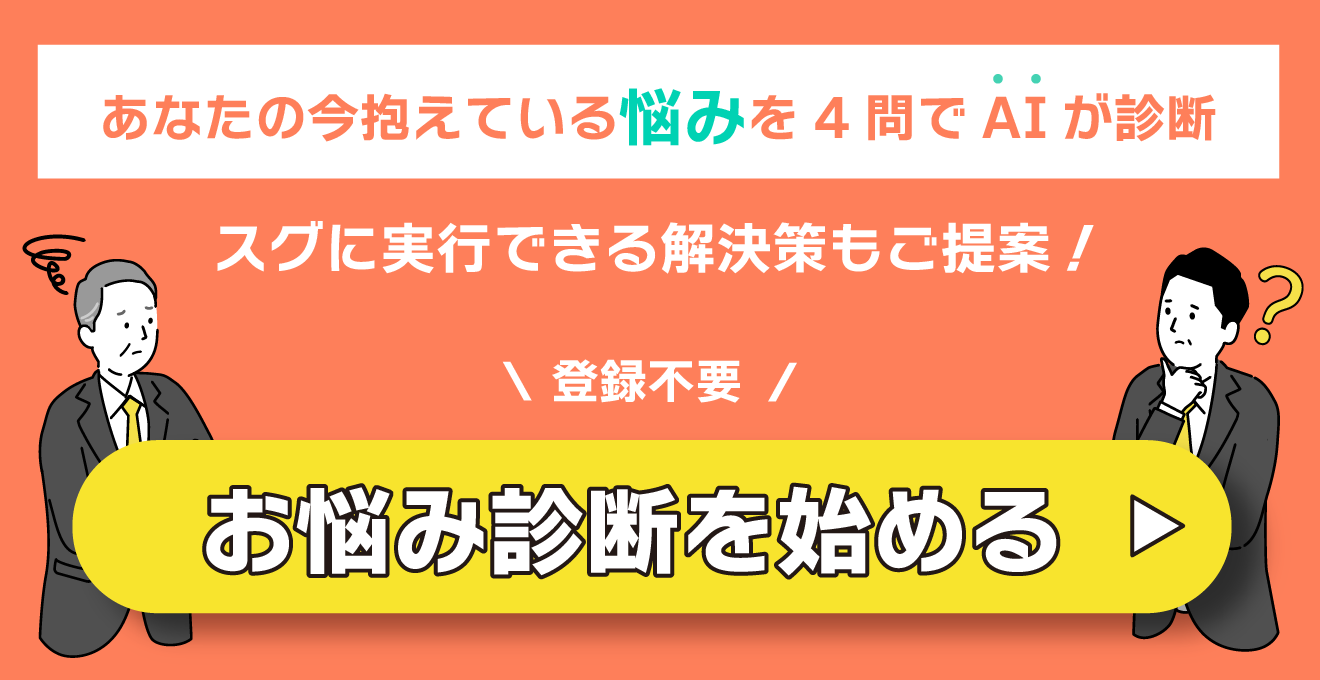AWS ECSとは
 AWS ECSとは、仮想サーバーを構築する際に使われるDockerコンテナの実行、停止、管理が簡単に出来るサービスです。
AWS ECSとは、仮想サーバーを構築する際に使われるDockerコンテナの実行、停止、管理が簡単に出来るサービスです。
正式名称をElastic Container Serviceといい、非常に高速で、仕事や利用者の増加に対応出来る能力に長けていることに高い評価を受けています。
Dockerコンテナへと対応しているため、Amazon EC2インスタンスのマネージドクラスターで、簡単にアプリケーションを実行することが可能です。
Dockerとは
Dockerとは、アプリケーションを素早く作成し、テストやデプロイすることの出来るソフトウェアのプラットフォームを指します。
AWSでDockerを運用することによって、管理者や開発者は分散アプリケーションがどれほどの規模であっても、低価格と高信頼性を実現した手段で、素早く実行やビルド、そして出荷することが出来ます。
AWS ECSのメリット4つ

AWS ECSを使用する上で、知っておきたいメリットが4つあります。
サーバーレスのオプションについて、アプリケーションの構築と管理に集中できること、安全で信頼性があること、コストの削減が出来ることです。
AWS ECSを使いこなすためには、正しい知識を身につけて理解を深めることが大切です。それでは1つ1つ説明していきます。
AWS ECSのメリット1:サーバーレスのオプション
ECSは、Fargateのサポートをすることにより、サーバーレスコンピューティングをコンテナに提供します。Fargateを使うと、サーバーのプロビジョニングと管理をしなくても良いので、リソースをアプリケーションごとに選択して支払うことが可能です。
以上のことから、アプリケーションが分離することでセキュリティが向上するというメリットがあるといえます。
AWS ECSのメリット2:アプリケーションの構築と管理に集中できる
ECSは、アプリケーションの作成と管理に集中しやすいというメリットがあります。
キャパシティプロバイダーを使用することによって、アプリケーションの需要に応じて振り分けられるコンピューティングキャパシティが決まります。
アプリケーションにfargateとEC2を、オンデマンド及びスポッドの価格設定オプションと組み合わせることで、柔軟性に富んだ使用が可能です。
AWS ECSのメリット3:安全性と信頼性
Amazon ECSでクラスター構成をする場合、Amazon VPCを自動で構築し、セキュリティグループやネットワークACLで管理することによって、そのままセキュリティ管理が出来ます。
また、個々の利用者それぞれのAmazon VPCによってコンテナが起動されるので、各自それぞれのAmazon VPCセキュリティグループを使うことが出来ます。他の利用者とリソースの共有をすることが無いので、より一層セキュアな環境を作ることが可能です。
AWS ECSのメリット4:コストの削減
AWS ECSでは、EC2spotインスタンスもしくはfargatespotタスクを使用することで、ステートレスなアプリケーションを行うためのオンデマンド価格と比較し、90パーセントもの割引が実現されます。
また、節約プランを使い、永続的ワークロードに対し50パーセントの割引も可能です。スポットインスタンスを、リザーブドインスタンス及びオンデマンドインスタンスと混合すれば、大規模なECSクラスターを安く簡単に実行することが出来ます。
AWS ECSの特徴7つ

AWS ecsを利用する上で、知っておきたい特徴が7つあります。
AWS Fargateのサポートについて、タスク定義について、コンテナの展開について、AMIについて、クラスターについて、バッチ処理について、AWSとの統合についてです。
サービスを使いこなすには、正しい知識を身につけて理解を深めることが大切です。それでは1つ1つ説明していきます。
AWS ECSの特徴1:AWS Fargate のサポート
Amazon ecsでタスクの起動を行うには、インスタンスタイプを適切に選択し、Auto Scalingの設定をし、クラスターのサイジングの管理をするといった、クラスターを立ち上げるための作業が必要となります。
しかしFargateのサポートがあれば、それらを全部無視することが出来るので、アプリケーションを定義したり、権限とスケーリングのポリシーを設定する作業に集中することが可能です。
AWS ECSの特徴2:タスク定義
AWS ecsでアプリケーション実行の準備をするためには、タスク定義の作成が必要となります。
タスク定義というのは、アプリケーションの構成に用いられるコンテナが記述されたテキストファイルを指します。
アプリケーションの仕組みを示した設計図と言えば分かりやすいでしょう。タスク定義は、アプリケーションのあらゆるパラメータを指定しています。
AWS ECSの特徴3:コンテナの展開
AWS ECSでは、様々なアプリケーションをコンテナ化することが出来るという特徴があります。
AWS ECSには単一もしくは複数のコンテナが、タスクという形で管理されています。コンテナインスタンスのリソースの余裕があれば、同じタスクを複数動かすことも可能です。
AWS ECSの特徴4:AMI
AWS ECSコンソールにてAWS ECSに向けて最適化されたAMIである、AWS ECS-optimized AMIを利用することが出来ます。(AMIとはAmazonマシンイメージのことを指します。)
サーバー作成の段階で、AWS ECSがすでに設定済みの環境が、敏速かつ一気に構築することが可能なので、AWS ECS環境の構築を短時間で行うことが出来ます。
AWS ECSの特徴5:クラスター
AWS ECSクラスターとは、サービスまたはタスクの論理グループをいいます。
クラスターへとAmazon EC2インスタンスを登録し、タスクの実行をすることが可能で、Fargate から提供されるサーバーレスインフラストラクチャを使うことも可能です。タスクをFargateで実行すると、Fargateでクラスターリソースが管理されます。
Amazon ECSを始めて使用する時、クラスターはデフォルトで作られます。ですが、幾つかのアカウントにクラスターを作ることで、リソースをクラスターごとに分けられます。
AWS ECSの特徴6:バッチ処理
AWS ecsには、バッチ処理によってアプリケーションの効率を上げることが出来るという特徴があります。
Amazon EC2の、スポットインスタンス、リザーブドインスタンス、オンデマンドインスタンスで、カスタムスケジューラーもしくはマネージドスケジューラーを用いてバッチワークロードを行うことが出来ます。
よって、効率の良いコストパフォーマンスや、効率の良いアプリケーションの配分が可能となるのです。
AWS ECSの特徴7:AWSとの統合
AWS ECSには、AWSと統合することで、より良いパフォーマンスを実現出来るという特徴があります。
AWSというのは、スケーラブルなサービスを長年運用して来た経験を元に身につけた技術によって作られています。
Amazon ECSは、他のAWSサービスと密に統合されているため、コンテナ化された様々なアプリケーションを作成そして実行するのに最適なソリューションを実現することが可能です。
AWS ECSの料金体系3つ

Amazon Elastic Container Serviceecs(ecs)の料金モデルには、 2つの種類があります。
Fargate起動タイプモデルと、Amazon EC2起動タイプモデルです。
それぞれ異なる特徴やメリットがあるので、使用の仕方に応じてモデルを選択すると良いでしょう。AWS OutpostsのAmazon ecsについても解説するので参考にして下さい。
AWS ECSの料金体系1:Fargate 起動タイプモデル
Fargate起動タイプモデルは、コンテナ化したアプリケーションに必要となるメモリリソースとvCPUへと料金が生じます。メモリリソースとvCPUは、コンテナイメージを得た時点から、AWS ecsタスクの終了する時点までを対象に計算されます。
試験的運用などの、コンテナ化したアプリケーションを使用する時間が定まっている場合には、こちらの料金体制がおすすめです。
AWS ECSの料金体系2:EC2 起動タイプモデル
Amazon EC2起動タイプモデルには、追加の料金が生じることはありません。
アプリケーションを保存したり実行したりするために作成された、EBSボリュームやAmazon EC2インスタンスなどのAWSリソースに対する料金のみが発生します。
使用した分の料金だけを支払うシステムで、初期費用や最低料金は必要ありません。コンテナ化したアプリケーションを常に動かしておく場合には、こちらの料金体制がおすすめです。
AWS ECSの料金体系3:Amazon ECS
「AWS OutpostsのAmazon ECS」 は「EC2 Launch Type」と同様のモデルです。
AWS OutpostsによるAmazon ECSの料金体制は単純で、クラウドと同様の形にあてはまります。
Amazon ECSコントロールプレーンは、Outpostsではないクラウド に存在し、コンテナインスタンスは追加の料金がかからず、 Outposts EC2の容量で実行されます。
AWS ecsを有効活用しよう

この記事では、Amazon ecsにどのような特徴があるのか説明してきました。
Amazon ecsは、コンテナ化したアプリケーションをAWSにて実行、そしてスケールすることの出来るサービスです。
さらに、他のAWSサービスと連携することで、あらゆる機能の実現が可能となります。低いコストで利用の出来るサービスですので、導入の検討をおすすめします。]]>
この記事の監修者・著者
-
株式会社オープンアップITエンジニア
-
未経験からITエンジニアへのキャリアチェンジを支援するサイト「キャリアチェンジアカデミー」を運営。これまで4500人以上のITエンジニアを未経験から育成・排出してきました。
・AWS、salesforce、LPICの合計認定資格取得件数:2100以上(2023年6月時点)
・AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
 AWS ECSとは、仮想サーバーを構築する際に使われるDockerコンテナの実行、停止、管理が簡単に出来るサービスです。
正式名称をElastic Container Serviceといい、非常に高速で、仕事や利用者の増加に対応出来る能力に長けていることに高い評価を受けています。
Dockerコンテナへと対応しているため、Amazon EC2インスタンスのマネージドクラスターで、簡単にアプリケーションを実行することが可能です。
AWS ECSとは、仮想サーバーを構築する際に使われるDockerコンテナの実行、停止、管理が簡単に出来るサービスです。
正式名称をElastic Container Serviceといい、非常に高速で、仕事や利用者の増加に対応出来る能力に長けていることに高い評価を受けています。
Dockerコンテナへと対応しているため、Amazon EC2インスタンスのマネージドクラスターで、簡単にアプリケーションを実行することが可能です。
 AWS ECSを使用する上で、知っておきたいメリットが4つあります。
サーバーレスのオプションについて、アプリケーションの構築と管理に集中できること、安全で信頼性があること、コストの削減が出来ることです。
AWS ECSを使いこなすためには、正しい知識を身につけて理解を深めることが大切です。それでは1つ1つ説明していきます。
AWS ECSを使用する上で、知っておきたいメリットが4つあります。
サーバーレスのオプションについて、アプリケーションの構築と管理に集中できること、安全で信頼性があること、コストの削減が出来ることです。
AWS ECSを使いこなすためには、正しい知識を身につけて理解を深めることが大切です。それでは1つ1つ説明していきます。
 AWS ecsを利用する上で、知っておきたい特徴が7つあります。
AWS Fargateのサポートについて、タスク定義について、コンテナの展開について、AMIについて、クラスターについて、バッチ処理について、AWSとの統合についてです。
サービスを使いこなすには、正しい知識を身につけて理解を深めることが大切です。それでは1つ1つ説明していきます。
AWS ecsを利用する上で、知っておきたい特徴が7つあります。
AWS Fargateのサポートについて、タスク定義について、コンテナの展開について、AMIについて、クラスターについて、バッチ処理について、AWSとの統合についてです。
サービスを使いこなすには、正しい知識を身につけて理解を深めることが大切です。それでは1つ1つ説明していきます。
 Amazon Elastic Container Serviceecs(ecs)の料金モデルには、 2つの種類があります。Fargate起動タイプモデルと、Amazon EC2起動タイプモデルです。
それぞれ異なる特徴やメリットがあるので、使用の仕方に応じてモデルを選択すると良いでしょう。AWS OutpostsのAmazon ecsについても解説するので参考にして下さい。
Amazon Elastic Container Serviceecs(ecs)の料金モデルには、 2つの種類があります。Fargate起動タイプモデルと、Amazon EC2起動タイプモデルです。
それぞれ異なる特徴やメリットがあるので、使用の仕方に応じてモデルを選択すると良いでしょう。AWS OutpostsのAmazon ecsについても解説するので参考にして下さい。
 この記事では、Amazon ecsにどのような特徴があるのか説明してきました。Amazon ecsは、コンテナ化したアプリケーションをAWSにて実行、そしてスケールすることの出来るサービスです。
さらに、他のAWSサービスと連携することで、あらゆる機能の実現が可能となります。低いコストで利用の出来るサービスですので、導入の検討をおすすめします。]]>
この記事では、Amazon ecsにどのような特徴があるのか説明してきました。Amazon ecsは、コンテナ化したアプリケーションをAWSにて実行、そしてスケールすることの出来るサービスです。
さらに、他のAWSサービスと連携することで、あらゆる機能の実現が可能となります。低いコストで利用の出来るサービスですので、導入の検討をおすすめします。]]>