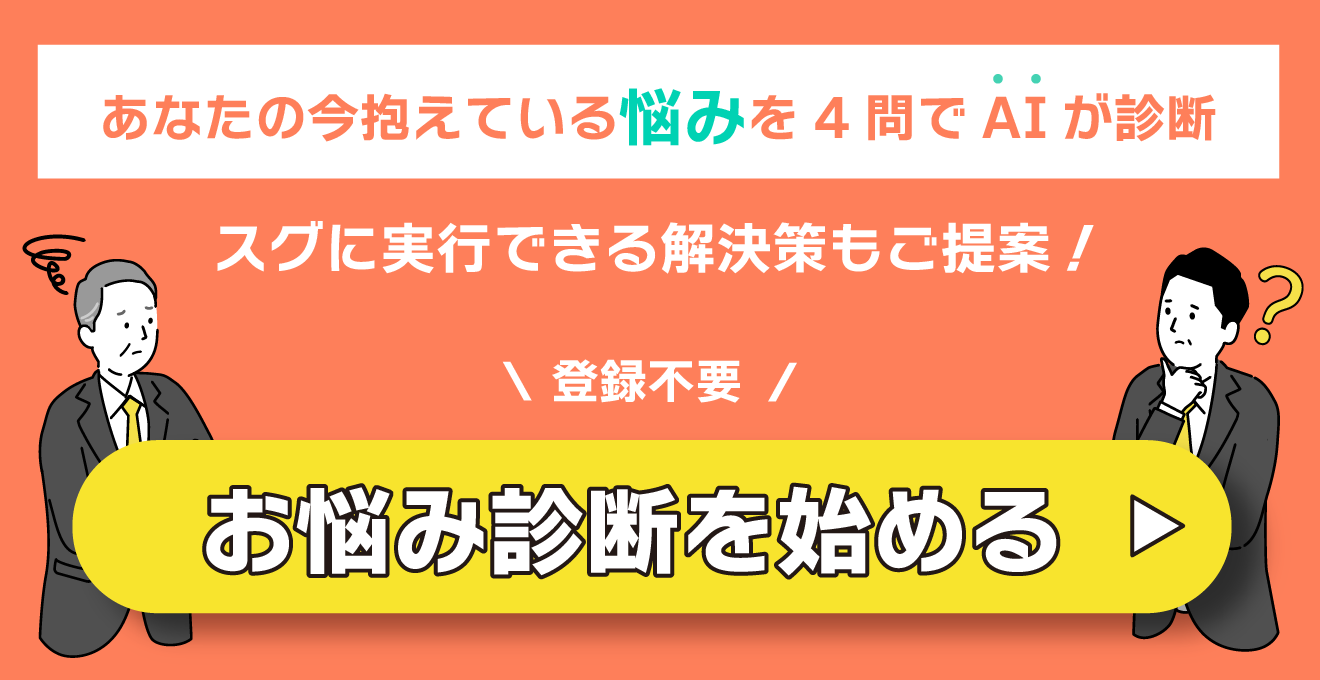ここでは将来開始される予定の「インボイス制度」について説明していきます。
フリーランスの方にとっては注意点が多く、仕事の依頼や収益に関わる可能性がある制度なので、必ずチェックしてください。
この記事の目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」の通称です。
「適格請求書」とは以下の内容が記載されている請求書のことで、これが「インボイス」と呼ばれています。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
- 消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
「適格請求書発行事業者」とは、上記の様式の請求書を発行できる者として税務署に登録した事業者のことです。
インボイス制度開始後は、取引相手が消費税の課税事業者である場合、相手方の請求に対して適格請求書を発行して保存する義務が生まれます。
インボイスがないと仕入税額控除を受けられない
インボイス制度が導入された後は、インボイスに記載されたもの以外の経費からは基本的に仕入税額控除を受けられなくなります。
つまり、仕入れにかかった消費税を、インボイスなしには差し引けなくなるということです。
「だったら相手にインボイスを発行してもらえばいい」と思うかもしれませんが、インボイスを発行できるのは課税事業者に限られます。
このためフリーランスの取引先は、フリーランスに「インボイスがないと私達が仕入税額控除を受けられないので、課税事業者になってください」と要求するかもしれません。
しかし、年間売上1000万円以下のフリーランス等は現在消費税の免税事業者であり、課税事業者になると消費税を支払う義務が生じるため、課税事業者になるのを拒否したくなります。
そうなると取引先は「ではインボイスを出してくれるところと取引します」と別の依頼先を探し始めるおそれがあります。
結果として、フリーランス側が仕事を失う可能性が出てくるのです。
インボイス制度導入によりフリーランスの働き方が変わる!?
上記のように、インボイス制度はフリーランスの仕事に大きな影響を及ぼしかねません。
これに対応するには何をするべきなのでしょうか?
まずは実施される日付を確認する
インボイス制度は段階的に実施されます。
まず、2019年10月1日~2023年9月30日の間は、現行法を維持した「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。
これは消費税率の区分を明確化するためです。
問題となるインボイス制度は、2023年10月以降に始まる予定です。
ただし経過措置として、登録事業者以外でも仕入税額控除から一定の割合を控除できる期間が設けられます。
- 2023年10月1日~2026年9月30日(控除率80%)
- 2026年10月1日から2029年9月30日(控除率50%)
これらはあくまでも予定に過ぎないので、導入までの日付をこまめに確認しておきましょう。
働き方を決める
取引先に事業者があって今後も取引を続ける場合は、課税事業者になるかならないかを決める必要があります。
課税事業者になれば消費税の支払義務が生じますが、前述のように課税事業者にならなければインボイスを発行できず、それが元で取引を停止される可能性があります。
場合によっては取引先と相談しながら今後の方針を決める必要があるかもしれません。
インボイス制度の詳細をチェックして対策を決めよう
インボイス制度の導入によって、現在免税事業者であるフリーランスは課税事業者になるか、免税事業者のままで仕事を続けるかを迫られる可能性があります。
免税事業者はインボイスを発行できず、それが理由で仕事が減る可能性もあるので、熟考のうえで働き方を選択しましょう。
この記事の監修者・著者

-
未経験からITエンジニアへのキャリアチェンジを支援するサイト「キャリアチェンジアカデミー」を運営。これまで4500人以上のITエンジニアを未経験から育成・排出してきました。
・AWS、salesforce、LPICの合計認定資格取得件数:2100以上(2023年6月時点)
・AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
最新の投稿
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】