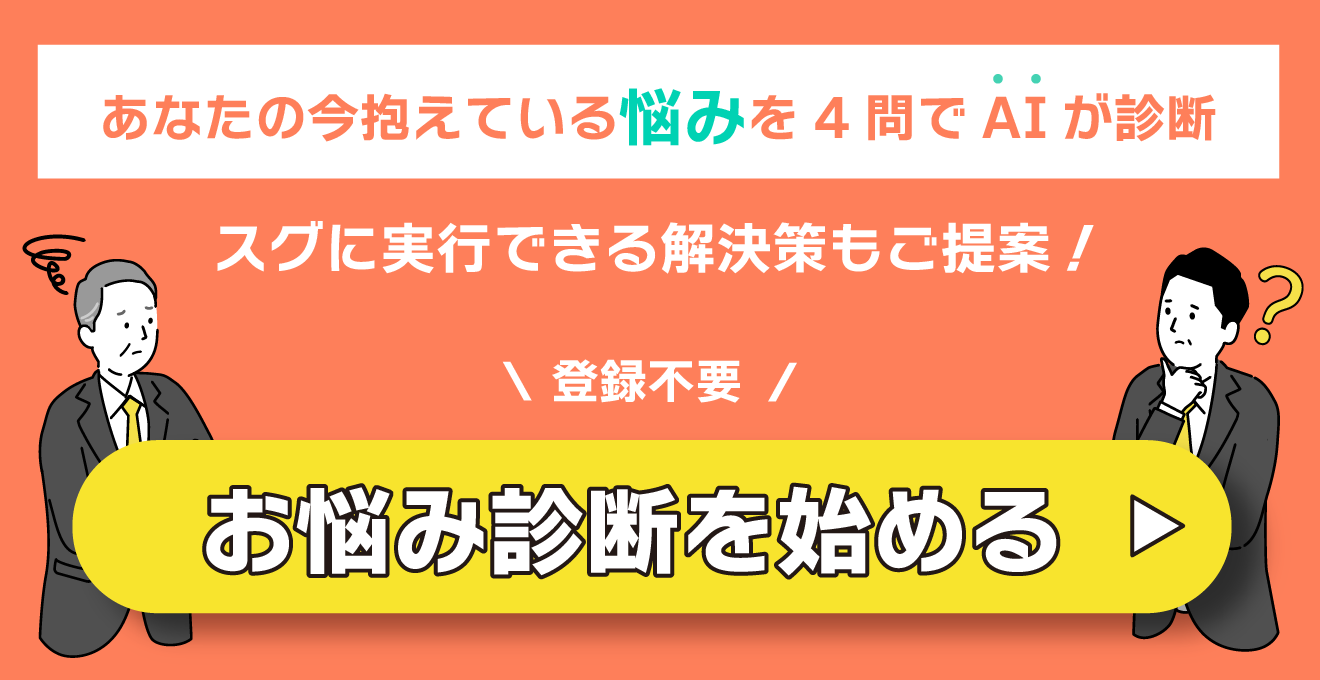この記事の目次
クラウドサービスを利用するメリット

クラウドサービスを利用することで得られるメリットがいくつかあります。
インターネット環境さえある場所なら、どこでもデータやファイルの管理・バックアップなどができる点や、 パソコンやスマートフォンとなったデバイスを気にせずにデータの同期ができる点などがあげられます。
ほかにも、社内にわざわざサーバーを設置して環境を整える必要がなくなるため、システムを導入する際の費用を低コストで抑えられる部分もメリットとなるでしょう。
AWSとは

AWSはAmazon Web servicesの略で、その名の通りAmazon社が提供するパブリッククラウドサービスです。
また、自社独自のデータ分析や商品の在庫管理を作り上げてきたインフラを、一般ユーザー向けに利用できるようにしたサービスとして開発されました。
パブリッククラウドサービスとしてもいち早く開始されたサービスでもあるため、現在では世界的に広く利用されています。
AWSだけじゃない!大手クラウドサービス

2020年現在パブリッククラウドサービスは、さくらインターネットのさくらのクラウドや、ニフティクラウド、富士通の富士通クラウド、AWSなどだけではありません。
Microsoft Azure・Google Cloud Platform ・IBM Cloud・Alibaba Cloudなどの、さまざまな会社が独自の技術を生かしたクラウドサービスも数多くあります。
大手クラウドサービスは世界的に広く利用され、特徴もそれぞれ異なります。アプリとの親和性や、安定な構成、学習ツールの利用可能などさまざまですが、共通して言えることはサービスの幅広さでしょう。
- Microsoft Azure
- Google Cloud Platform
- IBM Cloud
- Alibaba Cloud
AWSと4大クラウドサービスの強みを比較

パブリッククラウドサービスとして世界各地で使われている4大クラウドサービスと、AWSの強みや特徴、利用料金などを比較します。紹介するそれぞれの比較を参考にして、導入の検討に役立てていきましょう。
比較1:AWSの強み
AWSの強みは、ストレージやサーバーなどのインフラを届けるIaaSの種類が豊富であることです。そのため、パブリッククラウドとしてのシステム構築では、ミドルウェアやOSの制限も比較的少なくて済みます。
しかしAWSは制限が少ない分、利用者自身がソフトウェアのセキュリティ管理を行わなければならない点には注意してください。
AWSの利用料金
AWSの利用料金は比較的、複雑なものになっています。無料でありながら日本円で大まかな計算ができるWebサービスとして提供された「ざっくりAWS」で、使い方に応じた料金を確かめることができます。
また、公式で提供されている 「Amazon Web services Simple monthly Calculator」を使用すれば正確な料金の見積もりが可能ですが、入力項目の多さや英語が分かりにくい場合は、前者を活用してみましょう。
AWSの製品の特徴
AWSはハードウェアの基礎設計が比較的柔軟で行いやすい特徴を持つため、自社のエンジニアでカスタマイズしたい場合におすすめです。
ほかにもAWSは保存された動画をモバイルに対応するよう変換ができるため、世界中の企業に向けた多数のアプリデータが保管されています。
また、Amazon独自のアプリケーションサービスやアナリティクスツール、ストレージ機能などさまざまな分野に対応したサービスを同時に利用できる点もAWSの魅力と言えるでしょう。
比較2:Microsoft Azureの強み
Microsoft Azureの強みは、オフィスの定番ソフトをクラウド上で活用することができるOffice 365サービスです。
他社のクラウドサービスと比較しても、ビジネスアプリケーションを使ったオフィスワークは大きな利便性を持っているため、これからのビジネス環境を作り出すクラウドサービスとしての可能性を持っているサービスだと言えるでしょう。
Microsoft Azureの利用料金
Microsoft Azureの利用料金は、基本的に使用した量に応じた金額が請求される、従量課金制が採用されています。一方で、項目も多く素人には詳しい料金を計算することが難しい部分を持っているので、 公式サイトに用意された金額計算ツールを使って料金を見ていきましょう。
金額計算ツールではストレージやデータベースを追加したケースの料金を、仮想マシンの稼働時間を1時間とした際の計算ができるようになっているため、1日に何時間使うのか想定すれば簡単にどれくらいの料金がかかるのか調べられます。
Microsoft Azureの製品の特徴
Microsoft AzureはMicrosoft社の製品との連帯が取れる部分が大きな特徴です。またPaaSのアプリケーション環境を、クラウドで運用する会社や個人などに提供するサービスに力を入れています。
PaaSを使った環境を整えたり、そのままの状態で使用したい方にとってAzureは比較的扱いやすいです。そのうえ、Azure Marketplaceにはさまざまなアプリもあり、機能拡張もスムーズにできるでしょう。
比較3:Google Cloud Platformの強み
Google Cloud Platformの強みは、Google独自のネットワークで使えるさまざまなサービスを便利で機能的にしてくれることです。
ほかと比較するとシェア率が低いことから、日本語に翻訳された情報があまり多くありませんが、それでも世界中で利用できるパブリッククラウドとしての対応範囲の広さは、そのほかの製品と比較しても負けない性能を持っています。
Google Cloud Platformの利用料金
利用料金は従量課金制となっているため、利用した分だけ料金がかかる仕組みになっています。また、Google Cloud Platformは無料トライアル期間も設けられているので、一度使い勝手を確かめてみることも可能です。
そしてほかのプロバイダーよりも平均で60%低価格に設定されていることから、コストの低さも大きな特徴と言えるでしょう。
Google Cloud Platformの製品の特徴
Google Cloud Platformの製品の特徴は、GoogleマップやWindowsといったプラットフォームが元になったシステムの採用により、高速で安定したインフラを利用でき高性能なことです。
またGoogle app Engineなどのアプリケーションユーザーが増加した影響で、大規模なユーザー数にも耐えられるよう自動的にスケールされる仕組みがあります。
ほかにも、テラバイト単位のビッグデータを処理するBigQueryも活用でき、他社製品と比較しても機械学習で扱われるビッグデータの解析での使用を検討する価値はあるでしょう。
比較4:IBM Cloudの強み
IBMクラウドの強みは、自社社員でもデータにアクセスすることができないほどの、比較的強固なデータ暗号化を実現していることにあります。
また、セキュアなデータの活用を実現させるために作られたIBM watsonなどをはじめとするAIが組み込まれています。クラウド上でデータなどを強固なセキュリティで守りたい場合は、AWSや他社と比較しても優れているIBM Cloudを検討してみましょう。
IBM Cloudの利用料金
IBM Cloudの最低利用料金は、52,500円(税込)からとなります。そして、6ヶ月または12ヶ月、36ヶ月の利用の場合は割引対象となります。また30日間の無料トライアルもあるため、長く使用できるものかどうか確かめてみるのもいいでしょう。
AWSと比較しても、すぐにわかりやすい価格設定になっている点は魅力です。
IBM Cloudの製品の特徴
提供形態に幅広く対応することができるIBM Cloudは、オンプレミスのアーキテクチャに仕組みが似ていることから、運用設計を大きく変えずにスムーズな切り替えが行えます。
さらに、AIが組み込まれたセキュリティを活用すれば、使いやすい状態のままセキュリティ強化にもつながります。
比較5:Alibaba Cloudの強み
Alibaba Cloud(アリババクラウド)は中国と日本間をつなぐ専用線が引かれたり、中国でのシェア率の高さなど、アジア地域を中心としたパブリッククラウドサービスとしての将来性に期待されています。
また、アジアを中心とした活動を行う予定の会社や、中国とのつながりを持つ会社などであれば、よりスムーズなサービスの提供を受けることができるでしょう。
Alibaba Cloudの利用料金
Alibaba Cloudの利用料金は携帯幅に対して課金していく形となるため、データ転送のトラフィックそのものは無料扱いとなります。
そのほかのクラウドサービス同様、比較しきれない料金についても、計算できるツールなどがあるため、使用前にどれくらいかかるのか比較してみましょう。
Alibaba Cloudの製品の特徴
Alibaba Cloud製品の大きな特徴は他社との比較にならない程の、日本と中国間の通信がスムーズに行えるところです。
また、国際基準に従っている高水準のデータセキュリティを完備したインフラ基盤も利用可能になっています。Alibaba Cloudは、経済が成長し続けている中国との将来性あるグローバルビジネス展開を図る上でも、役立つ製品となるでしょう。
AWSの充実したトレーニング3選

AWSのパブリッククラウドを、より効率的に使えるようになるための学習ができる、AWSのトレーニング3つを紹介します。
さまざまな性能やアプリケーションを活用するためにも、AWSトレーニングそれぞれを比較しながら、レベルに合った知識を身につけましょう。
AWSのトレーニング1:無料のデジタルトレーニング
数百にも及ぶ無料のデジタルコースでは、多種多様なAWSクラウドにおけるスキルを学ぶことができます。さらに、ライブラリーの中から利用者のレベルに合わせたデジタルトレーニングを選ぶことができ、目的に合わせた選び方も可能です。
しかも、すべてオンデマンドで提供されていることから、自分の都合に合わせて視聴できるサービスで、比較的にAWS初心者用のものも多く扱われています。
AWSのトレーニング2:クラスルームトレーニング
クラスルームトレーニングは有償となりますが、自宅にいながら受講できるトレーニングです。AWSのエキスパートが技術的なことから知識的なものまで教えてくれたり、複雑になるトピックについて質問やディスカッションなど、リアルタイムで対応してもらうことができます。
そのため、デジタルトレーニングと比較すると、より高度な技術が学べるでしょう 。
AWSのトレーニング3:AWS 認定
AWS認定とは、AWSの専門知識を習得していることを証明する資格です。役割やレベルに応じた12種類の認定から、好きなものを選んで試験を受けることができます。
さらに、ワークショップなども用意されているので、 AWS認定に興味のある方は準備を始める意味でも調べてみてはいかがでしょうか。
ほかのトレーニングと比較すると自己学習も必要となるため、より幅広い知識が身に付くことでしょう。
パブリッククラウドはAWSと比較して選ぼう

パブリッククラウドの利用を考える際は、まずAWSと比較することから始めましょう。AWSよりも優れているところや、どのようなことができて、どのようなことができないのか比較表にしてみるなど、見極めることが大切です。
そして、ニフティクラウドやさくらクラウド、AWS以外の製品とも比較し、自分たちのビジネスや会社の目的に適したものを選択すれば、データの管理やネットワークの構築、レンタルサーバーの利用などがスムーズに行えるようになるでしょう。
この記事の監修者・著者

-
未経験からITエンジニアへのキャリアチェンジを支援するサイト「キャリアチェンジアカデミー」を運営。これまで4500人以上のITエンジニアを未経験から育成・排出してきました。
・AWS、salesforce、LPICの合計認定資格取得件数:2100以上(2023年6月時点)
・AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
最新の投稿
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】