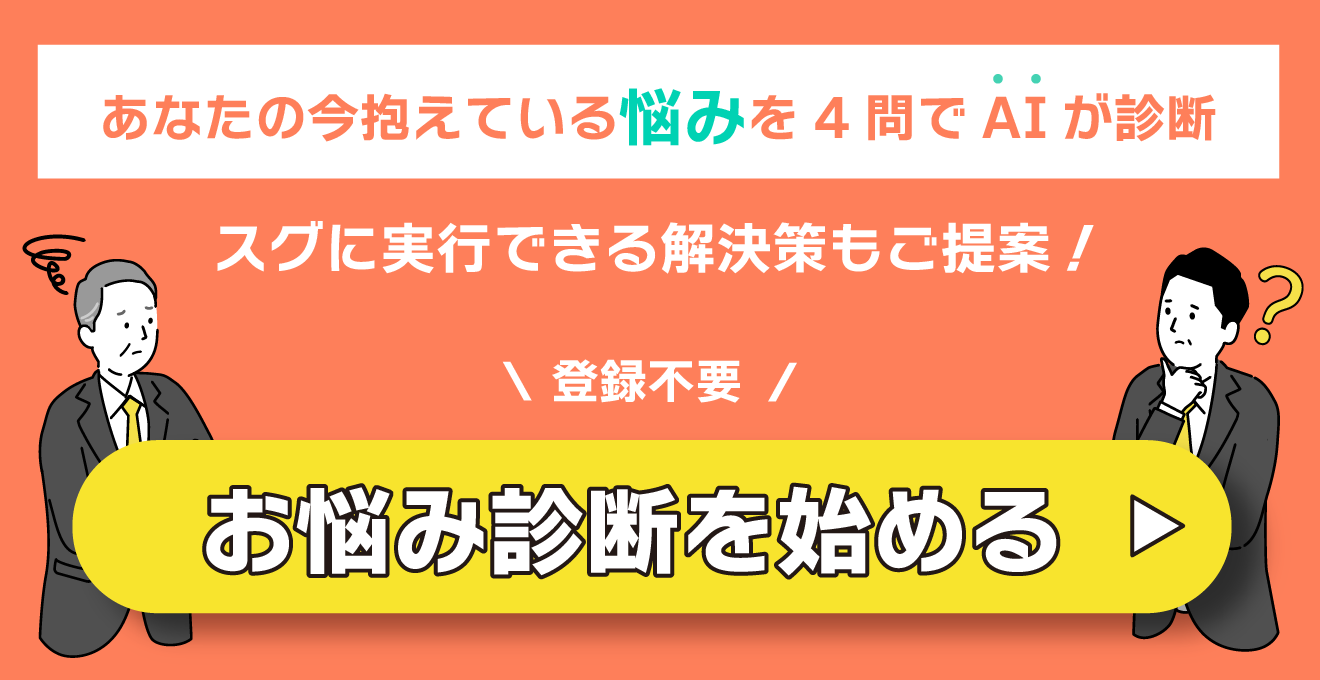この記事の目次
AWS Migration Hubとは

Amazon Web Services(AWS)のMigration Hubは、ソリューション間のサーバーやリソースの移行をモニタリングするサービスです。
複数の移行ツールにおけるステータスを一元的に表示します。これにより、リソースの移行状況を確認しやすくなり、プロセスの効率を高められます。
AWS Migration Hubの特徴

この項目では、AWSのMigration Hubの特徴についてご紹介します。
ステータスを一元的に表示するだけでなく、サーバーやリソースの関係性を特定する機能も備え、多方面から移行をサポートします。
注意点として、移行のプロセスを自動化する機能は搭載されていません。移行自体は手動で行う必要があるので、その点は留意しておきましょう。
使用する際は、併用するツールの特徴についても合わせて理解しておきましょう。
特徴1:リソースの移行を一元管理できる
Migration Hubは、リソースの移行を一元管理できます。
リソースの移行には複数のツールを用いることが多く、状況の確認に時間がかかりやすいという問題点があります。Migration Hubを用いることで、複数のツールの運用状況をまとめて確認できるようになり、この問題点を解消できます。
また、ステータスを一度に確認できることで、どのツールが最も効率的であるかを見極めることにも役立ちます。
特徴2:4種類の移行ツールに対応
Migration Hubは、4種類の移行ツールに対応しています。
AWSが提供するDatabase Migration Service(DMS)、Server Migration Service(SMS)、Application Migration Service(MGN)に加え、他社製ツールのATADATA ATAmotionにも対応します。
これらの運用状況を、一つの画面でまとめて追跡できます。
特徴3:サーバーやリソースをグループ化できる
Migration Hubは、サーバーやリソースをグループ化できます。
ネットワークを可視化する機能を搭載しており、サーバーやリソース間の依存関係を特定できます。これを用いて、移行を同時進行させたいリソース同士をグループとしてまとめられます。
移行にあたってのプランを作成する時に役立ちます。
特徴4:EC2 推奨事項によるコストの最適化
EC2 推奨事項は、サーバーのデータに基づいて最適なElastic Compute Cloud(EC2)インスタンスを推奨する機能です。
サーバーのプロセッサや論理コアの数、CPUやRAMの使用状況、AWSのオプションやリージョンなどのデータを収集・分析し、最も少ないコストで運用できるEC2のインスタンスタイプを提示します。これにより、コストの無駄を削減します。
推奨事項を生成する時は、RAMやCPUの使用率やリージョン、料金モデルなどの項目を指定できます。「これくらいの使用量にしたい」という指定をした上で、それに合わせたプランを提案してくれるので、推奨事項によってパフォーマンスが低下してしまう心配もありません。
AWS Migration Hubの開始方法

この項目では、AWSのMigration Hubの開始方法について、流れを簡単にご紹介します。
2つの方法が存在しており、移行を始める前にサーバー情報を検出するかどうかで手順が若干異なります。事前準備として、IAMユーザーを作成する必要があります。まだの場合は作成しておきましょう。
詳しい操作方法については、公式ドキュメントをご覧ください。
サーバー検出を行う場合
1つ目は、サーバーやリソースに関するデータを検出・取得してから移行を開始する方法です。
初期画面で[Get started with discovery(検出を開始する)]をクリックすることで、こちらのステップに移ります。
情報収集に特化したステップを用意することで、詳細なデータを参照できます。ステップが多い分だけ時間がかかりやすいので、速度を優先したい時は、検出を行わない方法を用いると良いでしょう。
ステップ1:検出
最初に、ツールをデプロイしてサーバーの検出を行います。
ツールには、Migration Hub Import、Discovery Connector、Discovery Agentの3種類があります。コンソールおよびドキュメントに比較表があるので、それを参考にして最適なツールを選択しましょう。
検出されたサーバーは[Servers (サーバー)]タグ内でリストとして表示され、詳細情報を確認できるようになります。
ステップ2:グループ化
検出されたサーバーをグループ化します。
[Servers (サーバー)]タグ内のリストから、グループ化したいサーバーのチェックボックスを選択して[Group as application (アプリケーションとしてグループ化する)]をクリックすることで、選択したサーバーがグループ化されます。
この時、新規のグループとして作成するか、既存のグループに追加するかを選択します。また、必要であればサーバーにタグやキーを追加できます。
グループ化が完了したら、次のステップへ進みます。
ステップ3:移行
次に、移行ツールを接続してリソースを移行します。
[Migrate (移行)] 内にある[Tools (ツール)]タグをクリックすると、使用可能なツールが表示されます。その中から使用するものを選択し、ツールごとの手順に従って移行を開始します。
ステップ4:追跡
移行が開始されると、同時に各ツールのステータスの追跡も始まります。
ダッシュボードを開くと、追跡中のステータスをチェックできます。ボード内の更新ボタンをクリックするかブラウザを再読み込みすることで、ステータスが更新されます。
なお、基本的にステータスは自動で切り替わりますが、手動で変更することも可能です。
サーバー検出を行わない場合
2つ目は、検出を行わず、直接サーバーを移行する方法です。
初期画面で[Get started migrating(移行を開始する)]をクリックすることで、こちらのステップに移ります。
こちらは移行とグループ化を同時に進行させるため、効率性が高いことが特徴です。ただし、検出ツールを用いた場合と比べて送られてくるデータ量が少ないので注意しましょう。もっと詳細なデータを得たい時は、検出ツールを用いた方法がおすすめです。
ステップ1:移行
最初に、移行ツールを接続してリソースを移行します。
[Tools (ツール)]タグから使用可能なツールを選択し、接続します。ここは検出を行う場合と同様ですが、この直後にグループ化を実行する点で異なります。
グループ化するサーバーは移行ツールから送信されてきたものから選択します。
ステップ2:追跡
移行が開始されると、同時に各ツールのステータスの追跡も始まります。
ダッシュボードで追跡中のステータスの確認や変更などが行えます。こちらも操作方法は検出を行う場合と同様です。
AWS Migration Hubの料金

AWSのMigration Hubは、すべてのユーザーが無料で使用できます。
ただし、DMSやSMSなどの移行ツールは有料であり、使用量に応じて料金が発生します。これらの料金についての詳細は、公式ページをご覧ください。
見積もりの際は、EC2を始めとした他のAWSサービスの料金も加味しておきましょう。
出典:AWS Migration Hub の料金
参照:https://aws.amazon.com/jp/migration-hub/pricing/
AWS Migration Hubでサーバー移行を効率化しよう

この記事では、AWSのMigration Hubについてご紹介しました。
複数の移行ツールの運用状況を一元表示することで、管理の簡易化やプロセスの効率化、コストの削減など、さまざまなメリットをもたらします。
AWSへのサーバー移行を考えている方は、利用を検討してみましょう。
この記事の監修者・著者

-
未経験からITエンジニアへのキャリアチェンジを支援するサイト「キャリアチェンジアカデミー」を運営。これまで4500人以上のITエンジニアを未経験から育成・排出してきました。
・AWS、salesforce、LPICの合計認定資格取得件数:2100以上(2023年6月時点)
・AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
最新の投稿
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】