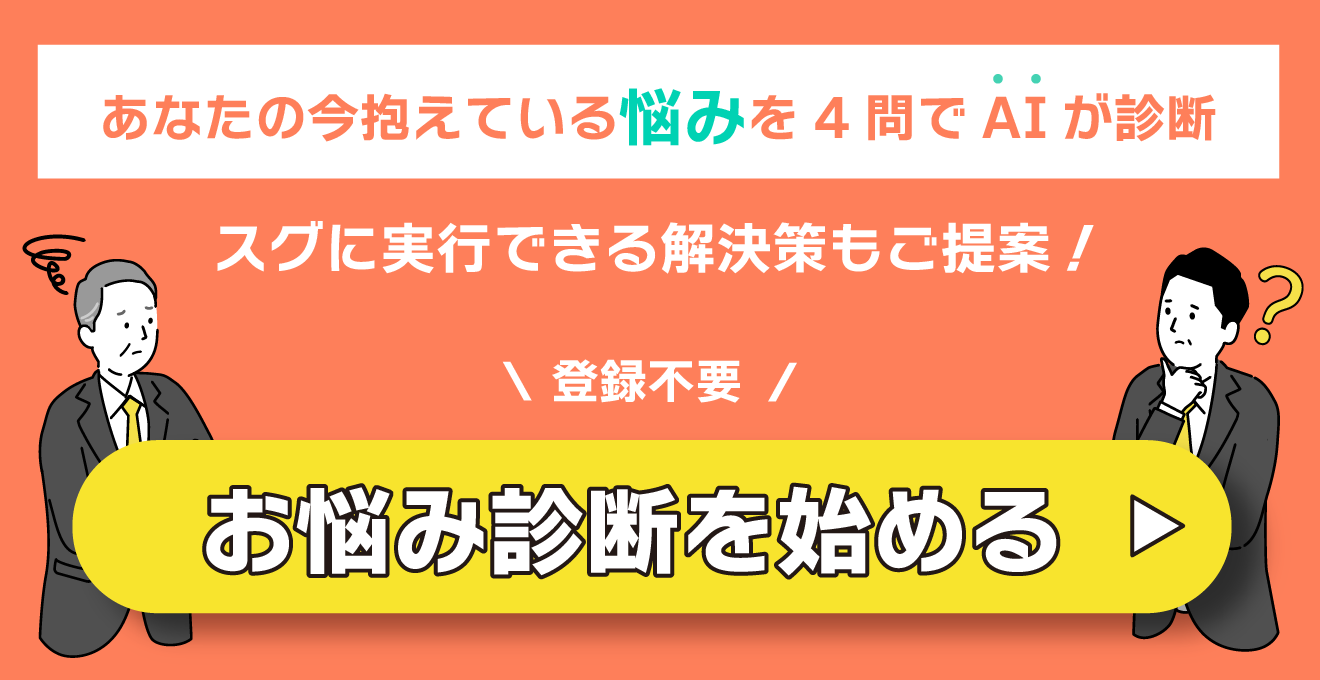この記事の目次
IoTとは?

IoTはInternet of Thingsの略で、身の回りのあらゆるモノがインターネットにつながる仕組みのことです。
人が操作してインターネットにつなげるだけでなく、モノが自らインターネットにアクセスするのがIoTの特徴です。
また、IoTはモノをインターネットにつなげることで、データを収集し、世の中のあらゆるシステムを効率よく使えるようにします。
IoTに関する資格は2つ!
IoTに関する資格として、IoT検定とIoTシステム技術者検定の2つがあります。IoTは新しい分野で、どちらの資格もまだできたばかりの資格です。そのため、一部準備中の資格試験もあります。
この記事では、この2つの資格について、それぞれの特徴や試験概要、資格を取得するメリットなどについて紹介していきます。
IoT検定について

IoT検定は、IoTに関わる知識やスキルを可視化して、IoTを広めることを目的にできた資格検定です。
IoT検定はIoTの技術面だけではなく、マーケティングやマネジメントなど、IoTを企画、開発、利用するために必要な総合的な知識を計る検定です。包括的な知識とスキルが求められるので、IoTを使った技術開発だけではなく、営業など仕事にも役立ちます。
IoT検定を受験するメリット
IoT検定受験のメリットについて紹介していきます。
IoT検定試験を受けることで、自分のIoTに関する知識を見直すきっかけが作れます。
また、IoTの導入、活用に関する知識が増えることで、IoTに関わるプロジェクトの提案や支援ができるようになります。
この資格があると他のIoT検定の資格保有者と交流ができるようになり、リアルな意見交換をしたりして、IoTの運用方法についてより深く学べます。
IoT検定の試験種別4選
IoT検定には、4つの試験があります。
IoT検定の試験はそれぞれIoT一般ユーザー向けと、IoTプロフェッショナル向けがあり、難易度別で分かれています。どの試験もIoTについて包括的な知識とスキルが必要です。
それぞれの試験に合格して資格を取得することで、IoTを企画、開発、利用するための知識があることを証明できます。
1:IoT検定ユーザー試験 パワー・ユーザー
IoT検定ユーザー試験パワー・ユーザーは、IoTに関する基本的な知識を計る資格試験です。
この資格試験は、IoTのセキュリティやデータベースなどの知識があるかどうかを問う試験です。
下記の表にある通り、40分間48問を解かなければならないので、速さと正確性が必要です。また、グレード制なので、IoTに対する理解度がどれくらいなのかを確かめられます。
試験形式 CBT 3者択一
試験時間 40分+アンケート
出題数 48問(8分野×6問)
評価方法 グレード制 ・グレードA=正答率86〜100% ・グレードB=正答率76〜85% ・グレードC=正答率66〜75% (グレードなし)
開催時期 通年受験可能
受験料金 8,800円(税込み)
2:IoT検定レベル1試験 プロフェッショナル・コーディネータ
IoT検定レベル1試験プロフェッショナル・コーディネータは、IoTの基礎的な運用ができるかどうかを計る資格試験です。試験は四肢択一形式で、60分で70問の問題を解きます。
この資格試験では、IoTプロジェクトに必要なツールの説明ができるかどうかを計ります。
この資格があると、専門家の指導の下でIoTプロジェクトに関わる業務ができることを証明できます。
試験形式 CBT 4者択一
試験時間 60分
出題数 70問
評価方法 合否(60%以上の正解で合格)
開催時期 通年受験可能
受験料金 11,000円(税込み)
3:IoT検定レベル2試験 プロフェッショナル・エンジニア
IoT検定レベル2試験プロフェッショナル・エンジニアは、現在準備中の資格試験です。
この資格試験では、IoTに関わる通信方法やプロトコルの設計、IoTプラットフォームの構築、セキュリティ対策の実施などの能力があるかを計ります。
また、この資格ではIoTの専門家として、IoTに関する全体の基本設計や詳細設計ができることを証明できます。
4:IoT検定レベル3試験 プロフェッショナル・アーキテクト
IoT検定レベル3試験プロフェッショナル・アーキテクトは、現在準備中の資格試験です。リリース時期は未定ですが、決まり次第公式のWebサイトで公開されます。
この資格試験はIoT検定の中でも最難関の資格試験です。IoTに関する幅広い知識と高度な能力が必要です。
この資格があるとIoTのプロフェッショナルであることが証明できます。
求められるスキルレベル
IoT検定で求められるスキルレベルは、試験によってさまざまです。
IoTに関する基礎知識があれば取得できる資格から、専門家指導の下でのIoTプロジェクトの業務遂行能力、IoTに関する設計能力などそれぞれ資格試験の難易度によって違います。
求めたられるスキルレベルの詳細については、IoT検定の公式サイトをご参照ください。
IoT検定合格に向けての学習方法
IoT検定の、資格試験合格に向けての学習方法の例を紹介します。
IoT検定の公式サイトで、公式テキストや、その他のIoT学習や資格試験に役立つ参考書を紹介しています。また、学習に役立つWeb記事も紹介していますので、参考にしてみてください。
問題集やWeb上にある疑似問題を使っての学習も、重要な部分を重点的に覚えられるのでおすすめです。
IoT検定の対象者
受験対象は特に限定はありません。
IoTに関する幅広い知識を問われます。IoTを活用するエンジニアの方やコンサルタント業務を手掛ける方など、さまざまな方が対象者です。
年齢や学歴、今までのIoTに関する経験も問われません。
IoTシステム技術検定試験について

IoTシステム技術者検定試験は、IoTシステムの構築、活用に関する知識を計る資格試験です。
この資格試験は、IoTシステムの企画、構築、活用、運用改善の効率を上げ、高い付加価値を生み出すための基礎知識の習得、そして優れたIoTの技術者になることを目的とした資格試験です。主にIoTビジネスに関わる方が対象です。
IoTシステム技術検定試験を受験するメリット
IoTシステム技術者検定試験のメリットについて紹介していきます。
IoTシステム技術者検定試験を受けることで、IoTに関する知識や技術を体系的に理解できるようになります。また、この資格はIoTの技術面にスポットを当てた資格なので、IoTを使ったサービスの開発や業務の効率化など、さまざまな場面で大きなヒントを得られます。
IoTシステム技術検定試験の試験種別3選
IoTシステム技術者検定試験には、レベル別に3つの試験があります。
この資格試験は具体的に、IoTの基礎知識を持つ基礎(IoTアドバイザ)、IoTシステム構築のための基本技術を持つ中級(IoTエキスパート)、高度なIoTシステムなどを構築する実践的な専門技術を持つ上級(IoTプロフェッショナル)の3つに分かれています。
1:基礎(IoTアドバイザ)
試験形式 4者択一
試験時間 60分
出題数 60問
評価方法 合否
開催時期 年2回(7月、12月)
受験料金 11,000円(税込み)
IoTシステム技術者検定試験の基礎(IoTアドバイザ)は、IoTシステム技術者検定の初級の資格試験です。
IoTに関する基礎知識を有することを認定する資格で、IoTに関する基本的な用語などを理解しているかを問う試験です。
この試験は4者択一形式で、60分で60問の問題を解きます。一定以上の正解率を超えると試験に合格でき、資格を取得できます。合格に必要な正解率の割合は公表されていません。
2:中級(IoTエキスパート)
IoTシステム技術者検定試験の中級(IoTエキスパート)は、IoTシステム構築に取り組むための基本技術を認定する資格試験です。
この試験では、IoTシステムの構築、活用に関わる技術知識について出題します。4者択一形式で、90分間で80問の問題を解きます。受講料金は15,400円で、年に2回開催しています。この試験も合格に必要な正解率は非公開です。
試験形式 4者択一
試験時間 90分
出題数 80問
評価方法 合否
開催時期 年2回(7月、12月)
受験料金 15,400円(税込み)
3:上級(IoTプロフェッショナル)
IoTシステム技術者検定試験の上級(IoTプロフェッショナル)は、IoTシステム技術者検定試験の中でも最難関の資格試験です。
この資格は、高度なIoTシステムを構築する実践的な専門技術を認定します。
この試験はIoTシステムに関する専門講座の受講後に論文を提出して、合否を判断します。専門講習は1.5日、論文は2時間かかります。年2回開催していて、受講料金は55000円です。
試験形式 専門技術講習受講後、論文の作成
試験時間 専門講習(1.5日)、論文(2時間)
出題数 論文(1500~1800文字程度)
評価方法 合否
開催時期 年2回(7月、12月)
受験料金 55,000円(税込み)
求められるスキルレベル
IoTシステム技術検定で求められるレベルは、それぞれの試験で違います。
基礎(IoTアドバイザ)ではIoTに関する基礎知識を理解する必要があります。
中級(IoTエキスパート)はIoTデータの活用技術などの、IoTシステムを構成するための基本技術の習得が必要です。
上級(IoTアドバイザー)では、IoTのシステム構築、活用に関する、より実践的な専門技術を求められます。
IoTシステム技術者検定試験合格に向けての学習方法
IoTシステム技術者検定試験合格に向けた学習方法について紹介します。
IoTシステム技術者検定は過去問を公開していないのですが、公式サイトでサンプル問題をダウンロードできるので、ぜひ活用してみてください。また、公式テキストを販売していて、IoTについてわかりやすく説明しています。
外部企業で、受験対策講座も開催しています。
IoTシステム技術者検定試験の対象者
基礎と中級は、IoTのシステムを構築して活用する目的で、技術的な知識を習得したい方です。受験資格の規定はありません。
上級は受験対象が限定されています。IoTシステム技術検定(MCPC)の中級合格者または情報処理学会のCITP資格保有者、早稲田大学スマートエスイー修了のいずれかの要件を満たしていることが条件です。
上級は資格要件の違いで受験料も異なります。また、MCPC合格者以外は団体申込です。
どちらの資格がおすすめ?

IoTを活用した技術の営業やコンサルタント業務を行いたい方はIoT検定、エンジニアとしての技量を証明したい方はIoTシステム技術者検定がおすすめです。
IoT検定は知識を問われるため、IoTの技術やメリットなどの説明業務の方に適しています。一方、IoTシステム技術者検定は技術の習得レベルを評価するため、エンジニアの方が自身の技量を確認可能です。
利用目的に合わせて、検定を選択します。
IoT検定とIoTシステム技術者検定試験以外で役立つ資格について

IoT検定やIoTシステム技術者検定試験以外でもIoTの開発に役立つ資格はあります。
ここまで直接IoTに関係した資格試験についてご紹介してきましたが、他にも役立つさまざまな資格があります。また、IoTに特化した資格ではないこともあり、他の分野のエンジニアを目指している方にもおすすめです。
ここではIoT検定とIoTシステム技術者検定試験以外で役立つ資格についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
エンベデッドシステムスペシャリスト試験
エンベデッドシステムスペシャリスト試験は、IoT時代に欠かせない組み込み系のスキルを認定する資格試験です。
情報処理技術者試験の1区分で、スキルレベル4に相当する難易度の高い試験のため高度情報処理技術者試験に含まれます。
難易度は高い試験ですが、現在組み込み系のシステム開発に携わっているエンジニアはもちろん、将来IoTに関わる仕事をしたいと考えている人にも適した資格です。
情報処理安全確保支援士試験
情報処理安全確保支援士試験は、サイバーセキュリティに関するスキルを認定する資格試験です。
情報セキュリティスペシャリスト試験の後継資格となっており、情報処理技術者試験とは異なる独立した試験です。しかしスキルレベルは4相当となっているため、非常に難易度が高い試験だと言えます。
情報セキュリティに関するスキルは年々重要度を増していることもあり、IoT分野をはじめすべてのIT人材に役立つ資格だと言えます。
2つのIoT資格を理解し転職に活かしましょう

ここまで、IoT検定とIoT技術者検定という2つの資格について紹介してきました。どちらの資格もIoTに関わる業務をする人にとって有用な資格です。また、新しくIoTを使った業務を始めようとしている方にもおすすめの資格です。
IoTに関わる業務をしている方はぜひ、IoTの資格にチャレンジしてスキルアップを目指してみてください。
この記事の監修者・著者

-
未経験からITエンジニアへのキャリアチェンジを支援するサイト「キャリアチェンジアカデミー」を運営。これまで4500人以上のITエンジニアを未経験から育成・排出してきました。
・AWS、salesforce、LPICの合計認定資格取得件数:2100以上(2023年6月時点)
・AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
最新の投稿
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】