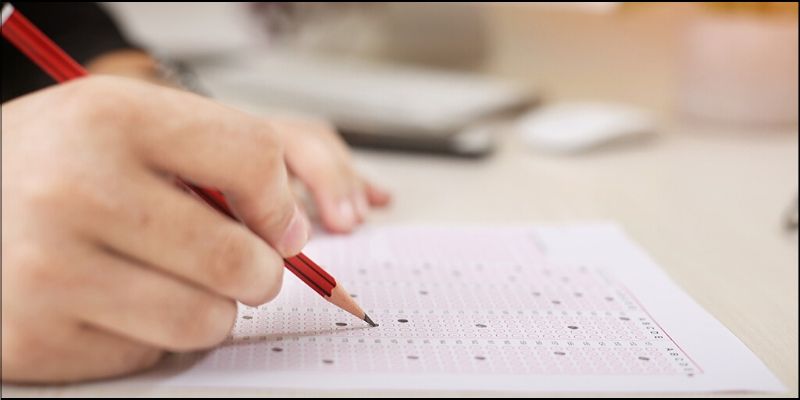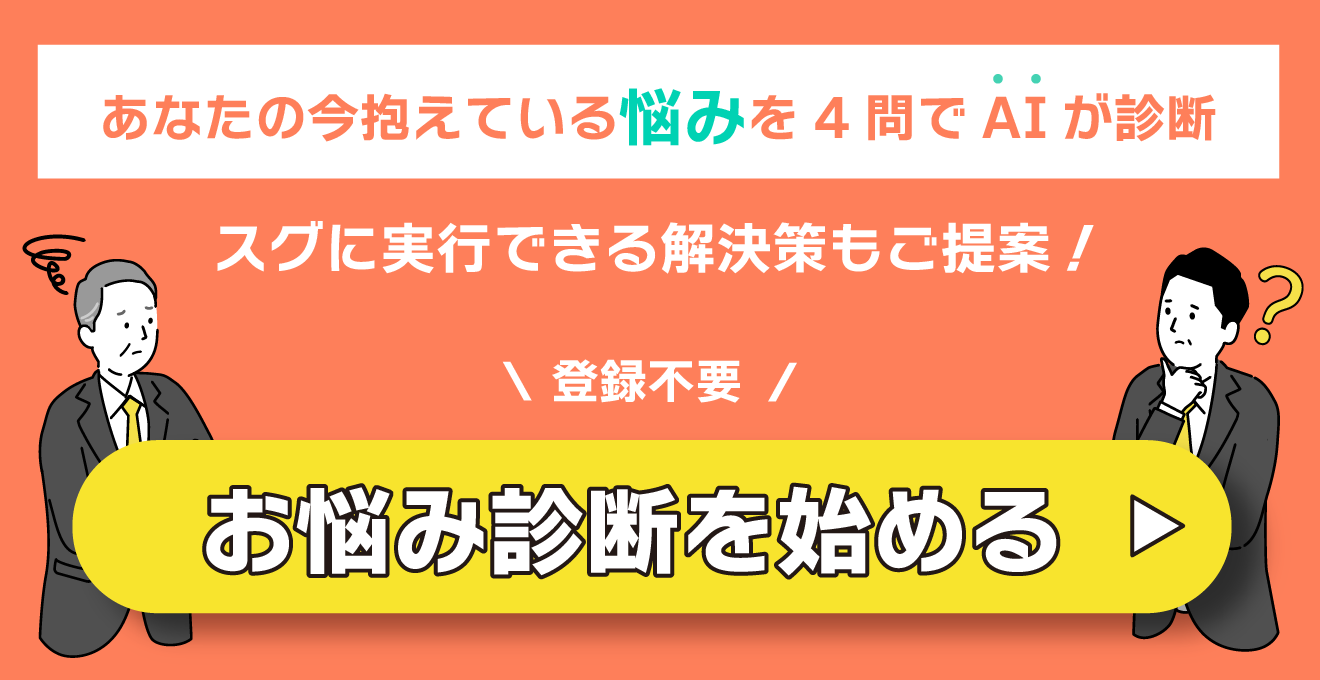この記事の目次
インフラエンジニアに資格は必要?
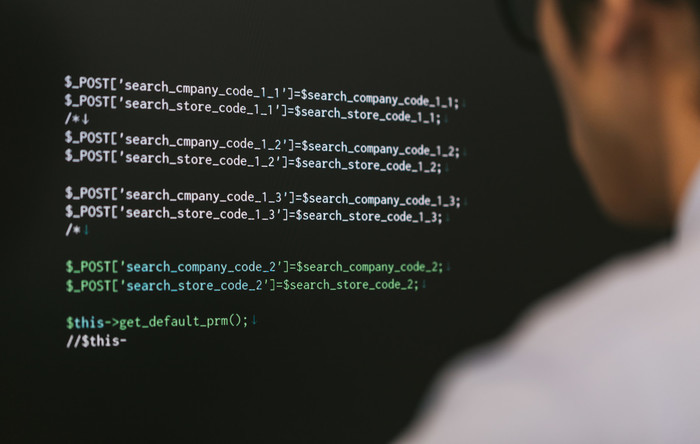
多種多様に存在するIT系の資格ですが、IT基盤を支えるインフラエンジニアという職種に限定すると、最適な資格というのはいくつかに絞られます。
インフラエンジニアとしての基本的ITリテラシーを問われるものや、ネットワークの構築・サーバー環境の構築についてのスキルを問うものが挙げられるでしょう。その中には難易度が比較的低いものから高いものまで、目的に応じてレベルが異なってきます。
インフラエンジニア向けの資格をまとめると以下のようになります。
インフラエンジニアに有利なおすすめの資格とは?

大きく2つに分けるなら、【国家資格】と【ベンダー資格(企業主催)】になるでしょう。
ベンダー資格については、主にシスコシステムズ社やオラクル社が主催する資格が人気となっており、さらにLinux関連を網羅する認定技術資格が中心になります。
国家資格については、基本から応用・専門分野までかなり広範囲なスキルを網羅しているので、体系的に学習したい人にとってもオススメの試験と言えるでしょう。
それぞれの資格について概要や特徴を次の章から詳しく見ていきましょう!
国家資格について

IT系の国家資格としてはいくつか区分がありますが、インフラエンジニアとして人気のあるのは以下の4種類でしょう。
ITパスポート
基本情報技術者(応用情報技術者)
ネットワークスペシャリスト
データベーススペシャリスト
ただし【ITパスポート】に関しては、どちらかと言うと初心者が体系的にITリテラシーを学習するための効率が良い資格という位置づけが強いです。まったくの初心者がインフラエンジニアを目指す際に、何から手をつけて良いか分からない場合に有効でしょう。
基本情報技術者
IT系の資格ではもっとも定番と言われているもので、基本的なコンピュータサイエンス、最新ITテクノロジー、システム開発、プロジェクトマネジメント、法務などの総合的な知識が必要になります。
インフラエンジニアとして必要な知識・情報処理能力に加え、経営・マネジメントなどIT分野においての幅広い知識が問われます。
難易度
誰でも受験することが可能なので、学生から社会人までおよそ15万人以上の方が毎年受験する人気の資格になっています。合格率は令和元年時点で28.5%です。最近では、プログラミング言語のCOBOLが廃止されて新しくPythonが加わったことでも話題になりました。
応用情報技術者はさらに高度なアルゴリズム、コンピュータシステム、セキュリティ、マネジメント全般、システム戦略、経営戦略などのスキルが求められます。
ネットワークスペシャリスト
Webサービスやアプリなどを安定して稼働させるために必要な環境の設計、構築、運用、保守、評価など全般のスキルが必要になります。特に最近では何らかの原因で発生した障害対応を円滑に進められるスキルも求められる傾向にあります。
必要な能力としては以下の通りです。
ネットワークシステムの要件定義
システム設計
システムの構築とテスト
システムの運用・保守
システムの管理全般
システムの評価
システム開発のコンサルティング
難易度
応用情報技術者試験よりも上位に位置づけられており、ネットワークについてより深い専門知識が必要となります。
実務経験のあるインフラエンジニアが受験するケースが多いにもかかわらず、合格率は低くかなり高度な試験です。
データベーススペシャリスト
ほとんどのWebサービスで必須となるデータベースの企画・要件定義・開発・運用・保守などの総合的なスキルが必要です。最終的には目的・要件に応じて最適な技術を選択して、高品質なデータベースを運用・維持できる人材が求められています。
必要な能力としては以下の通りです。
データベースの計画全般
データベースの要件定義
データベースの分析・設計
データベースの実装・テスト
データベースの運用・管理
難易度
こちらの試験もネットワークスペシャリストと同様に、応用情報技術者試験よりも上位に位置づけられており、実務経験のあるインフラエンジニアが受験するケースが多い中で、合格率の低い高度な試験です。IT系国家資格の最高峰の1つと言えるでしょう。
ベンダー資格について

ベンダー資格として定番なのは、LPIC/LinuC主催、シスコシステムズ社主催、オラクル社主催の資格でしょう。国家資格と違い、特定の専門分野をさらに深堀りした知識を習得できるものが多いです。
主なベンダー資格は、LPIC(Level1〜3)、LinuC(1〜3)、CCNA・CCNP・CCIE、ORACLE MASTER(Bronze,Silver, Gold, Platinum)などです。
LPIC・LinuCについて
主にLinux技術者のための認定資格を主催しているのがLPIC・LinuCですが、それぞれの違いは何でしょうか?
もっとも大きな特徴としては以下の通りです。
【LPIC】世界規模で主催されている業界標準の資格
【LinuC】日本国内で主催される日本の資格
つまり、LinuCは日本国内では通用するけどグローバル向けではないことになります。
ただし、LinuCは国内の大手企業がスポンサーになっていることもあり、国内における知名度は高く日本に最適化された試験内容になっている点も見逃せません。目的とする就職先や仕事内容によって、どちらの資格を取得するかを決めるのがベストでしょう。
難易度
LPIC・LinuCの資格には3つのレベルが存在します。
【Level1】Linuxの基本操作全般・システム管理の基礎
【Level2】高度なシステム管理・サーバー構築
【Level3】ファイルサーバー、セキュリティ、仮想化など
どちらの資格も出題される範囲や傾向は似ているので、レベルによって異なるスキルレベルを保有するわけではありません。
シスコシステムズ社の資格
世界的に知名度のあるネットワーク関連機器メーカーのシスコシステム社が主催する資格試験は、インフラエンジニアとして取得しておくと就職・転職に有利であるケースが多いことで人気があります。
何と言っても、ITの基盤を支えるネットワークシステムの知識・スキルを体型的に効率よく学習できるのと、それを証明できる世界標準の資格を得られるのは思っている以上に魅力的でしょう。
ただし、資格は1種類ではなく全部で5つのレベルが存在しています。
【CCENT】一般入門者用
【CCNA】初級レベル(9種)
【CCNP】中級レベル(7種)
【CCIE】上級レベル(6種)
【CCAr】最高水準の認定レベル
これからネットワークシステム関連の学習を始めるのであれば、エントリー向けとして提供されている【CCENT】が最適でしょう。ネットワークの基礎、LAN、ルーティング、インフラストラクチャー、メンテナンスなどの基礎知識を体系的に学べます。
また、一般的にインフラエンジニアが取得するのに最適と言われているのが【CCNA】です。
ネットワークの導入・構築・運用・保守などの基本的な部分を網羅的に判断できる能力が求められます。CCNAは専門的な分野によって9種類の試験に区分けされており、クラウド活用やセキュリティ対策など求められる能力が異なります。
これと同様により高度な知識を必要とする【CCNP】【CCIE】もそれぞれ専門分野によって数種類に区分けされています。
難易度
ネットワークに関する基礎知識から学べるので、ネットワークの実務経験が無くても目指せる資格です。インフラエンジニアを目指す人なら最初に目指すべき資格とも言えます。
試験はCBT方式で、自分で試験日を設定できます。旧CCNA試験では分野毎に試験範囲が分かれておりましたが、2020年から試験内容が刷新され、新CCNA試験では1つに集約されている為難易度が上がっている傾向があります。
ORACLE MASTER
日本オラクル社が主催するデータベースの技術者を認定する資格がORACLE MASTERです。オラクル社はデータベース業界では高いシェア率を誇っており、インフラエンジニアなら目にする機会も多いでしょう。同社が公式に認定するこの資格は事実上データベースのスキルを証明する唯一のものと言えます。
データベースの設計・構築・運用・保守・テストなどの総合的な知識を保有していることを証明できるだけでなく、就職・転職の際にも有利に働くことでしょう。
ORACLE MASTERは一般的に4つの種類に分かれています。
ORACLE MASTER(Bronze)
ORACLE MASTER(Silver)
ORACLE MASTER(Gold)
ORACLE MASTER(Platinum)
もっとも初心者向けなのが【Bronze】で1つずつレベルが上がり最終的に【Platinum】が高度なスキルを保有していることを証明できます。
難易度
Bronzeは入門者向けとなり、データベース管理システムの構築・運用・保守など基本的な部分と、SQL言語による基本的な文法などが問われます。
また、Silver以降はより高度な内容になると共に実務経験をベースにした内容も多くなり、バックアップ・障害対応・調整などや実技なども含まれます。
BronzeはさらにDBAとSQLに分けられ、SQLにはSQL基礎Iと12c SQL基礎があります。DBAと、SQL基礎Iか12c SQL基礎のどちらか1つに合格すると認定されます。
Bronzeの合格ラインは試験によって難易度が変わりますがおおよそ6割~7割ほどです。
インフラエンジニアが資格を取得するメリット4つ

これまでインフラエンジニアに最適なIT系の資格をいくつか見てきましたが、そのすべてが必要になるというわけではなく自分の目的や就職先をベースに検討することが重要です。
インフラエンジニアとして活躍する技術者は、1度習得した知識やスキルはどこにいっても通用するメリットがあるため、資格を更新し続けていれば強力なパートナーになってくれます。学習面から考えてもむやみに独学で取り組むよりも、体系的にまとまっている資格勉強を進める方が効率的でしょう。
つまり、資格を取得するという行動には大きく分けると2つの意味があり、1つは学習によるスキルアップ、もう1つは就職・転職を有利にするためと言えるでしょう。
資格取得のメリット1:スキルの証明になる
なんといっても、インフラエンジニアとしての自分のスキルを証明できることは、資格を取得して一番に得られるメリットです。
転職活動においては、履歴書に記載できるので書類選考も通りやすくなる可能性が高いです。自分の興味のある分野や、アピールしたい得意分野に適した資格を持っていれば効果的なアピールポイントになります。
そのためには自分のインフラエンジニアとしての将来性を見据えて、取得する資格を選ぶことも必要になってくるでしょう。
資格取得のメリット2:手当がつく
企業によっては、あらかじめ定められた試験を合格する、または資格を保有することで、一定の手当がついたり、給料アップしたりする可能性があります。
さらに書籍購入補助手当や規定回数までの受験料の負担など、あらゆる手段で雇用側がインフラエンジニアを手厚くバックアップしてくれるケースもあるでしょう。そういった環境が整っていれば、費用を気にせず資格取得に向けての学習に励むことができそうです。
資格取得のメリット3:幅広い業務に携わることができる
現在、インフラエンジニアの案件だけをみても、非常に多くのジャンルがあります。新たに獲得した知識を活用すれば、今まで自分が扱ったことのない分野の案件獲得の機会が増えたり、プロジェクトリーダーやプロジェクトマネージャーなどの重要なポジションにつくことができたりする可能性もあります。
資格を更新したり、さらに高い難易度の資格取得にチャレンジしたりすれば、インフラエンジニアとして多くのチャンスにつながることが期待できるでしょう。
資格取得のメリット4:現場で重宝される
近年では、仮想化・クラウド化によってインフラエンジニアでもプログラミング言語を学ぶ需要が高まってきました。各種試験においてもそういった新しい分野を出題範囲に加えることで、本当に現場で役に立つ実践的な知識の獲得につながっています。
また、プログラミングを習得すれば作業の自動化や効率化することができ、現場作業にいたってもそこにかかる多分な時間や労力が少なく済みます。
インフラエンジニアに有利な資格取得をめざそう

今回は、インフラエンジニアに最適な資格の種類について解説をしました。
最後に、もう一度ポイントをおさらいしておきましょう!
大きく分けると国家資格とベンダー資格が存在する
定番の資格としては情報技術者資格、LPIC・LinuC、CCNA、ORACLE MASTERがある
資格取得には自分のスキルアップと就職・転職を有利にするために取る目的がある
上記内容を踏まえて、ぜひ自分でもプログラミングに取り入れて活用できるように頑張りましょう!
この記事の監修者・著者

-
未経験からITエンジニアへのキャリアチェンジを支援するサイト「キャリアチェンジアカデミー」を運営。これまで4500人以上のITエンジニアを未経験から育成・排出してきました。
・AWS、salesforce、LPICの合計認定資格取得件数:2100以上(2023年6月時点)
・AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
最新の投稿
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】