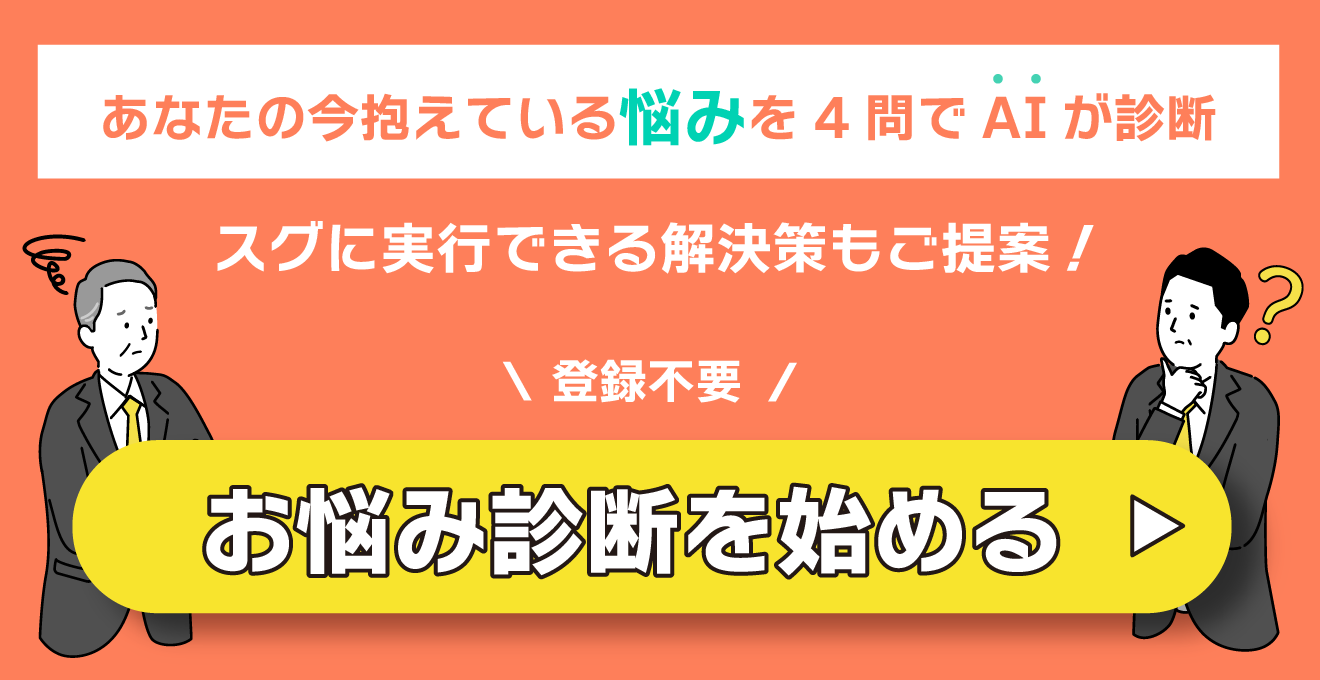この記事の目次
そもそもAWSとオンプレミスの違いは?

AWSは、Amazonが提供しているクラウドサービスを指します。クラウドコンピューティングを利用して、ストレージやデータサービス、サーバーなどの様々なサービスを貸し出しています。
一方オンプレミスとは、自社でサーバー等の設備を持ち、情報システムを運用する形態となっています。以前は主流となっていましたが、今ではクラウドサービスを利用した運営が主流となっています。
AWSとオンプレミスの大きな違いとしては、自社運用か外部運用かの違いになります。
AWSの7つの特徴

AWSにはオンプレミスと比較して特筆できる点が7つあります。AWS特有のセキュリティ対策や常に新サービスが追加される点、また低コストであることなど様々です。以下で、それらを1つずつ紹介していきます。
1:セキュリティ対策がなされている
AWSのセキュリティは、第三者の監査によるセキュリティやコンプライアンスの検証を実施しています。これにより、AWSでのセキュリティ面でのリスクを少ないものにしました。
AWSでは、セキュリティを最優先事項としてサービスを提供しています。クラウド環境自体の保守に関しては、AWSが責任を持っています。また、サービスを運用するためのサーバーのセキュリティにも、万全を期しています。
2:コストの負担が少ない
AWSではストレージやサーバーなどを、必要になったとき必要になった分だけ借りて利用することが可能です。サーバーを増築したり設定を切り替えたりと行った作業が不要になります。そのため、サーバーを自社に置くよりも最初に掛かる価格を低く抑えることが可能です。
加えて、AWSでは継続的な値下げを実施しています。保守費用の値上げが利用期間中に発生することもなく、むしろ値段が下がり続けるというメリットがあります。
3:新サービス・機能が追加される
AWSでは新しいコンテンツを素早く提供し続けています。AWSを利用することで、最新のテクノロジーを使ったサービスを自社に素早く取り入れて利用することが可能です。
サービスの種類が豊富であるほど、作業を集中させて行うことができ作業スピードの上昇に繋がります。また、新サービスを開発する時間も短縮することができるためより作業に集中できます。
AWSで提供しているサービスのラインナップは、AWSの公式サイトで確認することができます。
4:コンプライアンスに対応している
AWSでは常に最新のセキュリティが施され、様々な第三者機関の認証を得た環境を利用することができます。そのため、企業のコンプライアンスをより強固にさせることが可能です。
ただしAWSがすべてのコンプライアンスやセキュリティに対して責任を持つわけではなく、クラウド環境自体の責任を持ちます。利用者はクラウド内に存在するデータなどに関してのセキュリティに、責任を保つ必要があります。
AWSと管理、制御の内容を分けることで利用者に掛かる運用上の負担が軽減されます。
5:データ容量などの増加を気にしなくて良い
AWSは必要になった分だけ簡単にサーバーの数を増やすことも減らすこともできます。ストレージなども即座に増やすことができるので、データが増えていったとしても上限を気にする必要はありません。
利用者側で必要になったときに、AWSに申請することで数クリック、数分でサーバー台数を増減できます。
6:システムの障害が発生しづらい
AWSでは高いセキュリティを確保しており、AWSでの運用、管理、制御を行うことでシステム障害の発生を抑制しています。万が一のことが起こったときでも、常時対応のサポートがあるため素早い対応ができます。
7:トライアルが利用しやすい
AWSのサービスを初めて利用するときには、12ヶ月の無料トライアルを体験することが可能です。12ヶ月使用している間、料金発生なしでサービスを利用できます。AWSアカウントを作成して簡単に利用できるので、気軽に利用できます。
出典:AWSの無料トライアルで実際に体験
参照:https://aws.amazon.com/jp/free/start-your-free-trial/
オンプレミスの7つの特徴
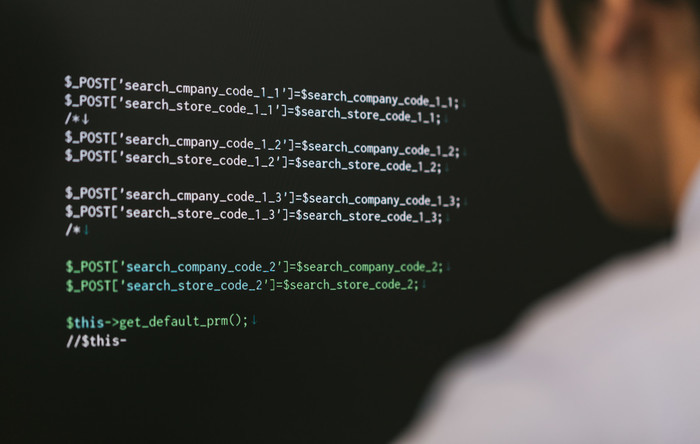
自社にサーバーを置くオンプレミスにも、AWSとは違う特徴があります。初期費用などのコストは掛かる傾向がありますが、自社にサーバーを置くことで、カスタマイズなどがしやすくなる、というメリットもあります。ここからは、オンプレミスの特徴7つを紹介していきます。
1:一定額のコスト設定にする事が可能である
オンプレミスは初期費用で多くのコストが発生しますが、それ以降は毎月一定額で運用することが可能です。
AWSでは毎月ストレージの増減が起きたりと、支出が一定ではなく不安定です。場合によってはオンプレミスを運用するよりもコストが掛かる場合もあり、不安要素になってしまいます。
しかし、オンプレミスであれば、毎月一定の固定費として安定したコストを出すことができます。
2:独自のセキュリティ対策が可能である
オンプレミスでは、自社基準でのセキュリティ対策ができます。
AWSではサーバー管理をAmazon側に委託するため、自社側で設定を工夫したり変えたりすることはできません。一方、オンプレミスでは自社で工夫することで、自社にとって必要なセキュリティ対策をピンポイントで行えるというメリットがあります。
3:自由にカスタマイズする事が可能である
オンプレミスは自社にサーバーを置き管理、運用をしていくことになります。AWSではクラウドサービスのため、カスタマイズができません。ですがオンプレミスを採用するとサーバーを自社の管理下に置くことになります。
自社サーバーということになるので、自社環境にあわせてサーバー設定を自由にカスタマイズすることが可能となります。
4:自社のシステムエンジニアに障害対応してもらえる
自社にサーバーを置き専門的なスキルを持つ人を雇うため、緊急の際には自社内の人に対応をしてもらえます。AWSではもし障害などの問題が発生したとき、Amazon側で復旧が行われますが、復旧の進捗を正確に把握することはできません。
オンプレミスでは、自社管理のサーバーなので自社で雇ったSEが復旧作業に当たるため、細かい進捗を確認することができます。
5:初期費用などコストが掛かる
オンプレミスではサーバーの設置やシステム構築を自前で行わなければなりません。その際の初期費用にかなりまとまった額が必要になります。
初期設定が終わり実際に運用を始めたあとも、システムを維持するための人材を雇い、サーバーの維持費や人件費などの他コストを毎月払い続けなければなりません。もちろん復旧の際に掛かる費用も自社負担です。
6:障害発生から復旧までにコストと時間が掛かってしまう
AWSでは多くの人材をサービスの維持に当てているため、障害が発生した際に素早く対応、復旧が可能です。対してオンプレミスを採用した場合には、自社内で障害対応から復旧まで行わなければいけません。
通常、企業では、AWS側よりも多くの人材を採用することはできません。そのため、必然的に復旧までの時間がかかります。また時間が掛かる分、コストが掛かってしまいます。
AWSを利用する場合は復旧の人材もコストもすべてAWS側が負担するため、自社はコストの心配をする必要がありません。
7:専門知識・技術を持つ人材を確保しなくてはならない
オンプレミスのシステムを維持、運用するために専門的な知識やスキルをもつ人材を雇わなければなりません。サーバー管理を社内で行っている以上、必然的に人材は必要になります。社内にスキルや知識を身に着けている人がいれば、その人をシステム構築や保守作業に割り振れます。
ですが、社内にスキルや知識を持つ人がいない場合、システムを構築する前に人材を確保する必要があります。
AWSとオンプレミスとの4つの連携サービス

ここまでオンプレミスとAWSの特徴と、それぞれのメリットを紹介しました。これまで紹介したメリットをあわせた、オンプレミスとAWSを連携させることのできるサービスがあります。ここではそのサービスを4つ紹介します。
1:AWS Outposts
AWS Outpostsはオンプレミスの形で、AWSを利用できるようになるサービスです。オンプレミスとAWSをハイブリッドさせたもので、自社内にAWSのサーバーを置き、独自性を保ちつつ管理や監視をAWSが行ってくれるようになります。
2:AWS Storage Gateway
AWS Storage Gatewayは、AWSのリソースとオンプレミスの容量を連携し、手間をかけずに利用が可能になるストレージサービスです。
オンプレミスでサーバーを運用しつつ、ストレージだけはAWSのものを利用するため、上限を気にする必要がないというAWSのメリットをハイブリッドさせた形になります。
クラウド上に直接データを書き込むのではなく、ユーザーがAWS Storage Gatewayに書き込んだあとAWS Storage Gatewayがクラウドに書き込むという手法を取ります。そのため、ユーザー側からはシームレスでクラウド情報管理ができるようになります。
3:AWS Ops Works
AWS OpsWorksは、AWSとオンプレミスを連携し、アプリケーション等の運用を自動化できるクラウド上のサービスです。これを利用することで、AWS上にオンプレミスと同等のシステムを構築することができるようになります。
AWS OpsWorksはサーバーのパッチ適応、アップデート、バックアップが自動的に実行されます。オンプレミスでは必要だった、独自の設定管理システムの運用や管理が必要なくなります。
連携したからといって、オンプレミスのシステムすべてに適用するわけではなくAWS OpsWorksのサポート範囲内のもので動くという点には注意する必要があります。
4:AWS Direct Connect
AWS Direct Connectはオンプレミスである端末などからAWSへインターネットを経由することなくプライベート接続ができるクラウド上のサービスのことです。高速で安定した通信ができるという特徴があります。
直接AWSのデータセンターに接続するのではなく、AWSと使用者の相手に相互で接続できるポイントを仲介して間接的に接続するという方法を取ります。
AWS Direct Connectを利用するメリットとして、セキュリティとコストが挙げられます。独立したネットワークを利用するので、安定したセキュリティの強い回線を使用することになります。また、データの転送コストも比較的安価に抑えることが可能です。
オンプレミスからAWSへ移行する場合の3つの注意点

いざオンプレミスからAWSに移行するとなったときは、いくつか注意しなければいけないことがあります。ここでは主に3つの注意点について焦点をあてて紹介していきます。
1:アプリケーション改修・動作テストが必要となる場合がある
移行する際に、AWS側でオンプレミス環境と同じものを用意できない可能性があります。その場合、新しい環境に適応させるためにアプリケーションの動作テストを行い、必要に応じて改修する必要があります。
環境適応させずとも動くときはありますが、AWSのサービスを有効利用するためには改修をしなければいけない場合もあります。
2:OS・ミドルウェアのバージョン確認
AWSに移す際に、オンプレミスで扱っていたOSやミドルウェアのバージョンが古いものであると注意が必要です。古いOSなどをそのまま使うことはできないため、新しい環境に今まで使っていたものを適応させなければいけません。
AWSでは使用できるOSやミドルウェアが決まっています。詳しくはAWSの公式サイトなどを確認してください。現状のオンプレミスで運用しているOSやミドルウェアが適用しているのか、変更の必要があるのかは確認しなければいけません。
3:クラスタ・負荷分散設定の見直し
オンプレミス環境でのクラスタ構成によっては、AWSでの実現方法を見直さなければならない場合があります。アプリケーション要件などで、特殊な負荷分散設定を行っている場合でも同様に見直しの必要があります。
AWSに移行する際には、殆どの場合別途検討が必要です。特にオンプレミスで共有ステレージ型のクラスタ機能を利用していた場合、そのままAWSに移行することは困難です。
AWSとオンプレミスの違いを知ろう

AWSとオンプレミス、それぞれに特徴が存在しており利用者によって適切なものは異なります。
AWSは初期費用のコストは低いですが、カスタマイズ性能は低く利用者独自のシステムを構築して行くことはできません。
オンプレミスは、カスタマイズ性能は高いですが、初期費用やサーバーの管理、保守費用、サーバー管理を行う人材の人件費など様々なコストが掛かります。
両者のメリットとデメリットを比較した上で、どちらを取るのか、もしくは連携サービスを利用するのかは、利用者側で判断しなければいけません。
この記事の監修者・著者

-
未経験からITエンジニアへのキャリアチェンジを支援するサイト「キャリアチェンジアカデミー」を運営。これまで4500人以上のITエンジニアを未経験から育成・排出してきました。
・AWS、salesforce、LPICの合計認定資格取得件数:2100以上(2023年6月時点)
・AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
最新の投稿
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職保安職(自衛官・警察・消防官など)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役保安職(自衛官・警察・消防官など)36人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に向いている人の性格・特徴ランキング【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】
- 2024年3月26日キャリア・転職クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)に必要なスキルランキング&スキルアップの方法とは?【現役クリエイター職(ライター・デザイナー・編集)64人が回答】